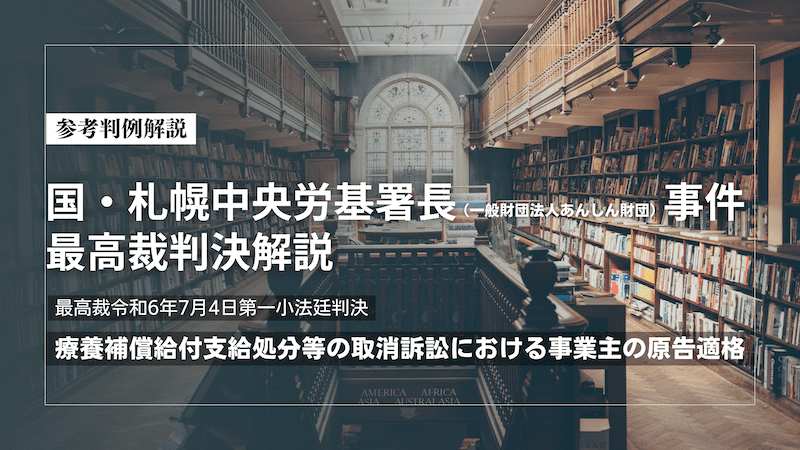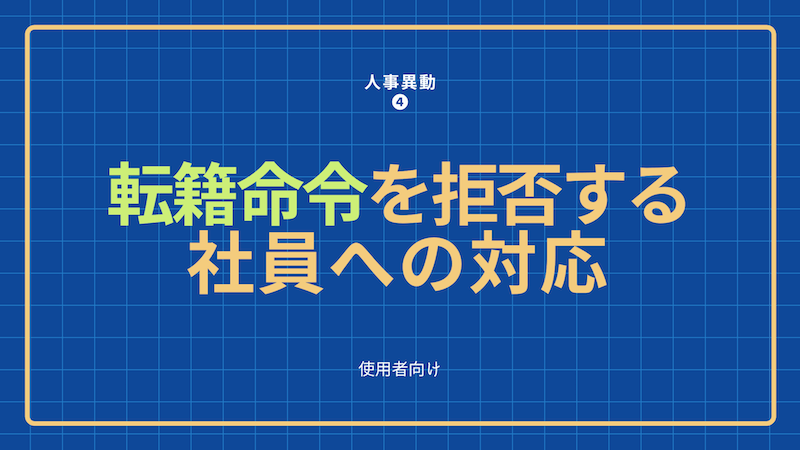はじめに
中小企業の倒産(破産)において、経営者(代表取締役)が会社の借入に連帯保証しているケースは非常に多く見られます。そのため、法人破産をしても代表者個人が多額の負債を抱え続け、再起不能に陥ることもしばしばです。そこで選択肢となるのが、代表者個人の破産も同時に申し立てる「同時申立」という方法です。
本記事では、法人破産と代表者個人破産の同時申立について、そのメリットとデメリットを具体的に解説します。「同時に進める方が便利」と思う一方で、費用面や書類準備の負担、さらには背任行為疑いへのリスクなど、考慮すべき点は少なくありません。しっかりと情報を整理し、自社の状況に応じて最善の選択をしましょう。
Q&A
Q1. 法人破産と個人破産を同時に行うメリットは何ですか?
主に以下のようなメリットがあります。
- 手続が一括で進むため、時間と労力を削減
- 書類準備や裁判所対応を同時進行で行える
- 連帯保証債務を含め、すべての負債を一度に整理
- 免責取得後、早期の再スタートが可能
Q2. デメリットとしてはどのようなことが考えられますか?
代表的なデメリットは以下のとおりです。
- 弁護士費用や裁判所費用が法人・個人分ともに必要(費用が高額化)
- 不正行為があれば両方の手続で問題化
- 同時申立のために書類量や手続がさらに増え、管理の負担が増加
- 破産管財人が法人・個人双方を調査する可能性が高まる
Q3. 同時申立をせず、法人破産だけ先に申立て、あとから個人破産を行うのはどうですか?
時期をずらす方法もありますが、偏頗弁済や資産移動の疑いが高まるリスクもあり、二度手間になるケースが少なくありません。また、手続期間が長期化し、代表者の負債問題が解決しないまま時間が経過するデメリットもあります。事案によっては、同時申立の方が効率的な場合が多いといえます。
Q4. 個人破産を同時申立した場合、自宅や車はどうなりますか?
個人破産において自宅や車など20万円以上の価値を持つ資産は原則換価の対象となります。ただし、住宅ローン特則が使える再生手続(個人再生)を選択すれば、自宅を残せる可能性もあります。
Q5. 同時申立を決める前に、どう判断すればいいのでしょうか?
連帯保証債務が大きいか、個人資産がどのくらい残っているか、税金などの免責されにくい債権があるかなど、総合的に判断が必要です。弁護士と相談し、メリットとデメリットをしっかり比較検討することが重要です。
解説
法人破産と個人破産の同時申立とは
- 手続の概要
法人破産とは株式会社や有限会社など法人格をもつ企業が裁判所を通じて破産する手続であり、個人破産は代表者個人が借金を整理するための手続です。同時申立では、会社と代表者個人の両方が同時に破産申立書を提出し、並行して審理が進められます。 - 連帯保証との関係
中小企業では、金融機関の融資に代表者個人の連帯保証が付されることがほとんどです。そのため、法人が破産しても保証人である代表者個人が負債を抱え続ける懸念が強く、個人破産が必要になります。同時申立なら両方の負債を一括で処理しやすいです。 - 管財人の選任
同時申立の場合、同一の破産管財人が法人・個人を担当することが多く、調査や清算手続きを一本化できる利点があります。一方、背任や資産移動が疑われると、より厳格な調査が行われる可能性が高まります。
メリット(詳細)
- 時間とコストの節約
法人と個人を別々に手続する場合、弁護士費用や書類作成の手間、裁判所への申立手数料などが二重に発生します。同時申立ならそれらを一本化でき、結果的に時間と費用が削減される場合があります。 - 手続の整合性が保ちやすい
個人破産と法人破産を同時に行うことで、財産目録や債権者一覧などの書類を連動させやすく、偏頗弁済の疑いを回避しやすいメリットがあります。破産管財人に対しても、一貫した説明を行いやすいです。 - 早期の再起が可能
法人の負債と個人の連帯保証債務が同時に清算されれば、代表者個人は免責を得ることで新たな事業や生活をスタートしやすくなります。無駄に手続期間が延びることなく、早期解決が期待できます。
デメリット(詳細)
- 費用が重なる可能性
同時申立を行う場合、弁護士報酬や裁判所への予納金は法人分と個人分が必要です。ただし、後から別々に申立てる場合と比較して、結果的に安くなるケースもあります。一度に高額な費用を用意しなければならない点はご負担となるでしょう。 - 書類量・調査範囲の拡大
法人と個人の財務状況を同時に詳細調査するため、管財人の目が一層厳しくなる場合があります。帳簿や資産移動の履歴を念入りに追及され、場合によっては不正行為が強く疑われることも。 - もし不正があれば両面で問題化
同時申立中に、代表者個人や法人で背任行為や資産隠しが発覚すれば、法人破産と個人破産の両手続が大きく停滞し、代表者の免責不許可の可能性もあります。
実務上の注意点
- 弁護士選び
破産申立には倒産実務に慣れた弁護士が必要不可欠。法人破産と個人破産を並行するため、書類作成・裁判所対応をスムーズに行える専門家を選ぶことが大切です。 - タイミング
差押えや強制執行が本格化する前に、同時申立を行うと個別の債権者対応が停止し、財産の処分が公平に進められます。遅れれば遅れるほど、資産流出や手続停滞のリスクが高まります。 - 背任行為の回避
同時申立だとしても、倒産直前に不適切な借金返済や資産移動があると偏頗弁済や詐害行為に該当しかねません。弁護士が介入した時点で勝手な資産処分を行わないよう注意しましょう。
弁護士に相談するメリット
- 同時申立が最適かどうかの判断
弁護士は、法人・個人の財政状況や債務構成をチェックし、同時申立が適切か、あるいは別手続が望ましいかを見極めます。結果的に手続コストとリスクを最小化する選択が可能です。 - 書類作成・申立代行
法人破産・個人破産それぞれに必要な書類作成や裁判所提出を弁護士が対応。経営者は情報提供に専念でき、事務的負担を減らせます。 - 背任行為や不正行為疑いの除去
弁護士が関与することで、資産移動や返済行為が破産法上問題ない範囲に収まるよう助言を得られます。偏頗弁済などに該当しないよう、事前チェックをします。 - 再起・免責後の支援
免責取得が認められれば、代表者個人は連帯保証債務などから解放されます。弁護士の後押しで新事業や再就職への準備をスムーズに進められるメリットがあります。
まとめ
代表者個人破産との同時申立は、中小企業経営者が倒産(法人破産)を検討する際に、連帯保証債務の解消を含めた最適な選択肢となり得ます。
メリット
- 法人・個人の手続を一度に済ませ、時間・コストを節約
- 連帯保証債務を含む全負債を一度に整理し、早期再起が可能
- 書類や裁判所対応を一本化し、手続の整合性を保ちやすい
デメリット
- 費用負担が大きくなる場合も(法人・個人双方の予納金、弁護士報酬など)
- 書類・調査範囲が拡大し、不正行為が疑われるリスク増
- 同時申立ならではの慎重な管理が必要
同時申立が適切かどうかは個々の財務状況や債権者構成、不正行為疑いの有無などによって変わります。弁護士に依頼し、法人破産・個人破産を最適な形で進めることで、代表者個人が再起しやすい環境を整えることが大切です。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス