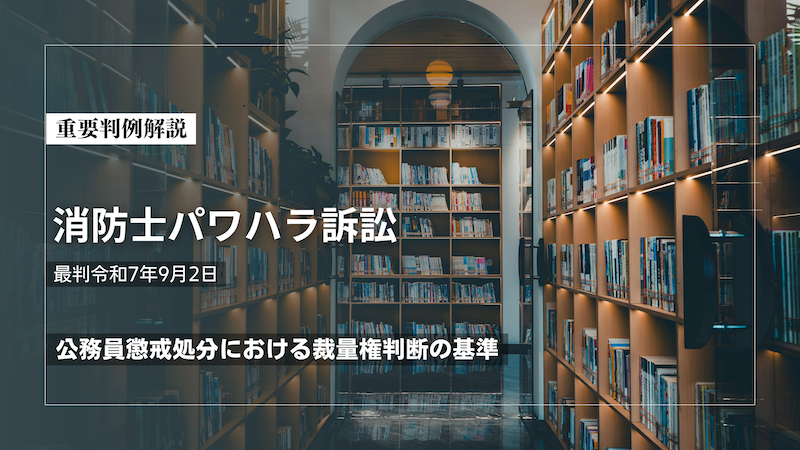AI音声での解説動画
本件のポイント
この度、最高裁判所第三小法廷は、2025年9月2日に、普通地方公共団体である糸島市消防本部の消防職員による部下へのハラスメント事案に関する2つの懲戒処分取消請求事件において、原審(福岡高等裁判所)の判断を破棄し、懲戒処分を適法と判断する判決を言い渡しました。
本件の最も重要なポイントは、公務員に対する懲戒処分、特に職場におけるハラスメント行為に対する処分について、懲戒権者(この場合は消防長)に与えられた裁量権の範囲を裁判所が極めて広く認めた点にあります。原審が、個々の行為の悪質性を限定的に評価し、懲戒処分を裁量権の逸脱・濫用であると判断したのに対し、最高裁は、ハラスメント行為の悪質性、継続性、対象者の多さに加えて、消防組織の特殊性(職務の危険性、規律、緊密な意思疎通の重要性)が組織に与える悪影響を重視し、懲戒処分が社会観念上著しく妥当を欠くとはいえないと結論付けました。これは、公務員のハラスメントに対する厳格な姿勢を示すものであり、今後の企業や行政機関におけるハラスメント対策や懲戒処分の運用に大きな影響を与えるものと考えられます。
事案の概要
本件は、糸島市消防本部に勤務していた二人の消防職員(以下、それぞれ「被上告人X1」「被上告人X2」と称します)が、任命権者である糸島市消防長から部下に対する言動等を理由に受けた懲戒処分に対し、その取消しを求めた事案です。被上告人X1は停職6月の懲戒処分(以下「本件処分1」)を、被上告人X2は懲戒免職処分(以下「本件処分2」)を受けました。
両事件は、いずれも地方公務員法29条1項(職員が同法や規程に違反した場合、または全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合などに懲戒処分ができる旨の規定)に基づき処分がなされています。
1. 事件1:停職6月の懲戒処分取消請求事件(最高裁令和6(行ヒ)214号)
(1) 被上告人X1の行為内容
被上告人X1は、消防隊の分隊長として、小隊長であるAの下で訓練を取り仕切る立場にありました。被上告人X1は、採用後間もない部下Bに対し、以下に挙げるような複数のハラスメント行為(以下「本件各行為1」)を行いました。
- 本件行為1:2011年10月頃から2012年3月頃までの間、夜間に複数回にわたり、Bの身体を鉄棒に掛けたロープで縛った状態で懸垂をさせ、Bが力尽きて手を放すと、そのロープを保持して数分間宙づりにし、さらに懸垂を指示した。
- 本件行為2:雑巾掛け競争を行わせ、これに負けたペナルティとして腕立て伏せ等をさせた。
- 本件行為3:2011年10月から11月頃、はしご車の誘導訓練終了後、Bが敷板を粗雑に扱ったことを理由に、「お前帰れ。二度と消防に来るな。今すぐ帰れ。消防署辞めて帰れ。」などと暴言を吐き、Bの肩やヘルメットの上から頭部を叩き、胸倉をつかんで揺さぶり、突き飛ばすなどして消防署の敷地の外に押し出した。さらに、敷板に複数回「敷板さん、ごめんなさい。」と謝罪の言葉を述べさせた。
- 本件行為4:2011年11月から12月頃、Bがした指差し呼称が不十分であるとして訓練のやり直しを命じた際、ヘルメットの上からBの頭部を複数回叩いた。
被上告人X1は、本件処分以前に部下に対する暴言を理由に文書による訓告を受けていました。
(2) 各審級における判断の概要
- 第一審・原審(福岡高等裁判所):停職6月の懲戒処分は重きに失し、裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用した違法なものであるとして、被上告人X1の請求を認容しました。原審は、本件行為1、2は被上告人X1が主導的役割を果たしたとはいえず、トレーニング方法として不適切だが逸脱の程度は特段大きくない、本件行為3、4も指導が度を超えたもので暴力等の内容や程度が著しいとはいえず、Bの軽率な言動が契機となった面もあると評価しました。また、Bは負傷しておらず、被上告人X1に過去の懲戒処分歴がなく個別の注意も受けていないこと、一応反省の態度を示していること等を考慮しています。
- 最高裁判所:原審の判断は是認できないとして破棄自判し、被上告人X1の請求を棄却しました。
2. 事件2:懲戒免職処分取消等、懲戒処分取消請求事件(最高裁令和6(行ヒ)241号)
(1) 被上告人X2の行為内容
被上告人X2は、平成5年4月に消防職員として採用され、消防士長、消防司令補を経て、小隊長、警防課通信指令第3係長を務めるなど、消防職員を指導すべき立場にありました。被上告人X2は、平成15年頃から平成28年11月までの十数年もの長期間にわたり、少なくとも10人に上る部下に対し、以下に挙げるような極めて多数のハラスメント行為(以下「本件各行為2」)を行いました。
- 各指導
採用後間もない部下に対し、鉄棒に掛けたロープで身体を縛って懸垂させ、力尽きた後も数分間宙づりにして更に懸垂するよう指示したり、熱中症の症状を呈するまで訓練を繰り返させたり、体力の限界のため倒れ込んだことに対するペナルティと称して更に過酷なトレーニング(顔面に面体を装着しての腕立て伏せ、同僚を担いで走行など)をさせるなどの行為。 - 各発言
部下に対する嫌悪、苛立ち、悪感情を主な動機とする暴言が多数含まれており、恐怖感や屈辱感を与えたり、人格を否定したりするもののみならず、その家族をも侮辱する発言(例:「お前帰れ。二度と消防に来るな。」「ぶっ殺すぞ、お前。」「お前は俺の近くにおるな、死ね。」「お前の娘もそうなるっちゃろ。」「宇宙は太陽が中心やろうが。ここでは俺が太陽たい。」「俺はしつこいけん、一生根に持つけんな。」など)が含まれていました。
被上告人X2には、本件処分以外の懲戒処分歴はありませんでした。しかし、糸島市消防本部では、2016年6月頃に実施されたアンケートでパワー・ハラスメントの蔓延が指摘され、同年7月頃には、被上告人X2らによるいじめやしごき等を原因とする若手職員の退職・休職、職場復帰への反対が多数の職員から表明されるなどの事態が生じていました。
(2) 各審級における判断の概要
- 第一審・原審(福岡高等裁判所)
懲戒免職処分は重きに失し、裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用した違法なものであるとして、本件処分2の取消請求および損害賠償請求の一部(慰謝料100万円)を認容しました。原審は、各指導は訓練として通常行われる範囲を逸脱しているものの、逸脱の程度は特段大きいとはいい難い、各発言も言い過ぎの面や表現が適切でなかったに過ぎない部分があると評価しました。また、被害職員に重大な負傷は生じておらず、被上告人X2に過去の懲戒処分歴がなく個別の注意も受けていないこと、一定の反省の態度を示していること等を考慮しています。 なお、原審は損害賠償額として慰謝料100万円を認めましたが、弁護士費用相当損害金を追加して、合計110万円及びこれに対する遅延損害金の支払いを認める限度で原判決を変更しました。 - 最高裁判所
原審の判断は是認できないとして破棄自判し、被上告人X2の請求(取消請求および損害賠償請求)をいずれも棄却しました。
主な争点
本件の主な争点は、以下の2点に集約されます。
- 被上告人X1及び被上告人X2がそれぞれ行ったハラスメント行為が、地方公務員法29条1項に定める懲戒事由に該当するか否か。
- 糸島市消防長が被上告人X1に対して行った停職6月の懲戒処分、および被上告人X2に対して行った懲戒免職処分が、懲戒権者に与えられた裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したものとして違法となるか否か。特に、原審(福岡高等裁判所)がこれらの処分を違法であるとした判断の妥当性が問われました。
裁判所の判断理由(最高裁)
最高裁は、原審の判断を是認できないとして、以下の理由により両事件の懲戒処分が適法であると判断しました。
- 懲戒処分の判断基準
最高裁は、公務員に対する懲戒処分について、懲戒権者は、諸般の事情を考慮して、処分をするか否か、また、いかなる処分を選択するかを決定する広範な裁量権を有していることを改めて示しました。そして、その判断が社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したと認められる場合にのみ、違法となるという従来の判例の立場を維持しています。 - 各行為の非違の重大性
最高裁は、原審とは異なり、両被上告人の行為の非違の程度を極めて重く評価しました。
(1) 事件1(停職処分)に関する被上告人X1の行為
被上告人X1の本件各行為1について、最高裁は「身体的な苦痛のみならず強い恐怖感や屈辱感を与えるものであって、Bに傷害を負わせるものであるか否かにかかわりなく、訓練等の際の部下に対する指示や指導としての範ちゅうを大きく逸脱した極めて不適切な言動である」と指摘しました。被上告人X1が主導したとはいえないものが含まれているとしても、その非違の程度は重いと断じています。また、被上告人X1が、過去に部下に対する暴言を理由に文書訓告を受けていたにもかかわらず、本件各行為を継続したことは非難を免れないとしました。
(2) 事件2(免職処分)に関する被上告人X2の行為
被上告人X2の本件各行為2について、最高裁は各指導(宙づり懸垂、熱中症訓練、過酷なペナルティ等)が「訓練やトレーニングに係る指示や指導としての範ちゅうを大きく逸脱するもの」であり、各発言も「部下に恐怖感や屈辱感を与えたり、その人格を否定したりするもののみならず、その家族をも侮辱したりするものも含まれている」と指摘しました。これらの行為は「部下に対する言動として極めて不適切なものであり、長期間、多数回にわたり繰り返されたものであることにも照らせば、その非違の程度は極めて重いというべきである」と判断しました。
3. 消防組織の特殊性と組織への悪影響
最高裁は、両事件を通じて、消防組織の特殊性を考慮し、ハラスメント行為が組織に与える悪影響を重視しました。
- 職務の性質
消防職員は、火災等の現場において住民の生命や身体の安全確保のための活動等を行うという職務の性質上、厳しい訓練が必要となる場合があるとしても、本件各行為のような指示や指導としての範疇を大きく逸脱する行為は許容される余地はないとしました。また、悪感情等に赴くままに行われた部分が大きかったことから、被上告人X2の行為に酌むべき事情はないとしました。 - 組織の秩序・規律
消防組織においては、職員間で緊密な意思疎通を図ることが職務の遂行上重要であると強調しました。両被上告人の行為は、部下を指導すべき立場にあった者が行ったものであり、職場環境を著しく悪化させ、消防組織の秩序や規律に看過し難い悪影響を及ぼすものと評価されました。特に、免職事案では、被上告人X2らによるいじめやしごき等により若手職員の退職が相次いでいたことや、多数の職員が被上告人X2の職場復帰に反対する旨の書面を提出した事実が、悪影響の大きさを裏付けるものとされました。 - 林道晴裁判官の補足意見
免職事案の林道晴裁判官の補足意見では、消防職員の職務遂行上、上下関係に基づく厳しい訓練が必要となる場合がある一方で、そのような上下関係が、職務遂行の必要性とは裏腹に、職場内での優位性を背景とした不適切な言動が行われる危険を孕んでいると指摘されました。この危険性は、本件のみならず他の消防職員の事案からも窺われるとし、各消防本部において認識され対策が実施されていることを踏まえ、対策を確実に実施していくことが望まれると強調しています。
4. 原審の判断の誤り
最高裁は、原審が「個々の行為を単体で評価すると免職が重きに失する旨判断するものということができる」と指摘し、本件各行為が全体としてどのような悪影響をもたらすものであるかを十分に評価することを怠ったと判断しました。最高裁は、非違行為による影響について、行為の態様の極めて不適切さ、期間の長さ、行為の回数、被害者の多さ等の諸事情を基礎として評価する必要があることを示したものです。
裁判所の判断内容(結論)
最高裁は、上記の理由に基づき、懲戒権者である糸島市消防長の判断が、社会観念上著しく妥当を欠くものであるとはいえず、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したとはいえないと結論付けました。
その結果、
- 事件1(停職6月の懲戒処分取消請求事件)
原判決(福岡高等裁判所判決)を破棄し、第一審判決を取り消し、被上告人X1の請求を棄却しました。 - 事件2(懲戒免職処分取消等、懲戒処分取消請求事件)
原判決中、上告人(糸島市)敗訴部分を破棄し、第一審判決中、上告人敗訴部分を取り消した上で、被上告人X2の請求(懲戒免職処分取消請求および損害賠償請求)をいずれも棄却しました。
これにより、両被上告人の懲戒処分は最終的に適法と判断され、確定しました。
実務に与える影響
本最高裁判決は、公務員、特に高い規律が求められる消防組織におけるハラスメント事案に対する懲戒処分のあり方について、以下の点で重要な実務的示唆を与えます。
1. 懲戒権者の裁量の広範な尊重と総合的判断の重要性
本判決は、懲戒処分、特に公務員に対する懲戒処分においては、裁判所が懲戒権者の判断に介入するハードルが極めて高いことを改めて明確にしました。行為の悪質性、継続性、被害者の人数、そして組織全体に及ぼす影響を総合的に評価することが不可欠であり、個々の行為を単体で過小評価すべきではないと示唆しています。企業や行政機関の懲戒権者は、ハラスメント行為に対して処分を検討する際、行為の詳細、背景事情、被害の程度、加害者の反省の有無、過去の処分歴といった個別事情に加え、職場全体の士気、組織の秩序・規律、信頼性への影響といった広範な要素を考慮に入れるべきであるという姿勢が求められます。
2. ハラスメント対策のさらなる強化の必要性
消防組織のような特殊な職場環境(高い規律、緊密な連携、危険な職務)においても、指導の名を借りたハラスメント行為は決して許容されず、組織の運営に重大な悪影響を及ぼすことが明確にされました。これは一般企業においても同様であり、ハラスメント防止のための実効的な対策がますます重要となります。
具体的には、以下の点に注力すべきです。
- 明確な規範の策定と周知
ハラスメントの定義、禁止行為、懲戒処分の基準を明確にし、全職員に周知徹底することが不可欠です。糸島市ではハラスメント防止規程があったにもかかわらず事案が発生しており、規程だけでなく、その実質的な運用が重要です。 - 管理職・監督職への教育強化
部下を指導する立場にある者こそがハラスメントの加害者となり得ることを認識させ、適切な指導方法、アンガーマネジメント、コンプライアンス意識の徹底を図る必要があります。本件でも、小隊長・分隊長といった立場にあった者が加害者となっています。 - 相談窓口の設置と運用
被害者が安心して相談できる体制を整備し、プライバシー保護を徹底した上で、迅速かつ適切に対応することが求められます。 - 客観的かつ徹底した調査体制
ハラスメントの申告があった場合、被害者、加害者、関係者からの事情聴取を公正かつ客観的に行い、事実関係を正確に把握する調査委員会等の設置が重要です。原審が個々の行為を単体で評価し、最高裁が全体として評価すべきとしたように、行為の継続性や組織全体への影響を多角的に検証する視点が必要です。 - 厳正な処分と再発防止策
ハラスメント行為が認定された場合には、その内容、期間、影響に応じた厳正な処分を躊躇なく行い、再発防止に向けた具体的な措置(研修、配置転換、監視体制など)を講じることが必要です。免職事案では、懲戒免職処分取消後、多数の職員が職場復帰に反対する嘆願書を提出しており、職場環境への配慮が不可欠であることを示唆しています。
3. 組織文化の醸成
林道晴裁判官の補足意見が示唆するように、組織内の上下関係がハラスメントに繋がる危険性があることを認識し、健全なコミュニケーションと相互尊重の組織文化を醸成することが極めて重要です。厳しい訓練や指導が必要な職場であっても、それが人格を否定したり、不当な身体的・精神的苦痛を与えたりするものであってはなりません。組織全体でハラスメントを許容しないという強いメッセージを発信し続けることが求められます。
4. 今後の実務上の留意点
懲戒処分の有効性を確保するためには、以下の点にご留意ください。
- 事実認定の正確性
ハラスメント行為の有無、内容、期間、頻度、被害の程度などを客観的な証拠に基づいて正確に認定することが不可欠です。曖昧な事実認定は処分の違法性を招くリスクがあります。 - 処分の均衡性
認定された非違行為の内容や重大性、被害の程度、加害者の反省の有無、過去の処分歴、職場への影響などを総合的に考慮し、他の類似事案との比較も踏まえながら、処分が重すぎないか、軽すぎないかを慎重に判断する必要があります。本判決は、原審が個々の行為を単体で評価しすぎた点を批判しており、行為が継続的に繰り返された場合や、複数人に対して行われた場合には、非違行為全体の悪質性を高く評価する必要があります。 - 手続きの適正性
懲戒処分は、地方公務員法や関連規程に定められた手続きに厳格に従って行われる必要があります。例えば、事前の聴聞手続きの保障、弁明の機会の付与などは、被処分者の防御権に関わる重要な要素です。
本判決は、地方公務員のハラスメント行為に対する懲戒処分の適法性を広く認めたものであり、今後のハラスメント対策や懲戒処分の運用において、企業や行政機関がより厳格な姿勢で臨むべきことを示す画期的な指針となるでしょう。
当事務所では、ハラスメント問題に関するご相談、懲戒処分に関するアドバイス、社内研修など、幅広くサポートを提供しております。お気軽にご相談ください。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、様々な分野の法的問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。ご興味をお持ちの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
ご相談はお気軽に|全国対応
長瀬総合法律事務所は、お住まいの地域を気にせず、オンラインでのご相談が可能です。あらゆる問題を解決してきた少数精鋭の所属弁護士とスタッフが、誠意を持って対応いたします。
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス
企業が法的紛争に直面する前に予防策を講じ、企業の発展を支援するためのサポートを提供します。
複数の費用体系をご用意。貴社のニーズに合わせた最適なサポートを提供いたします。