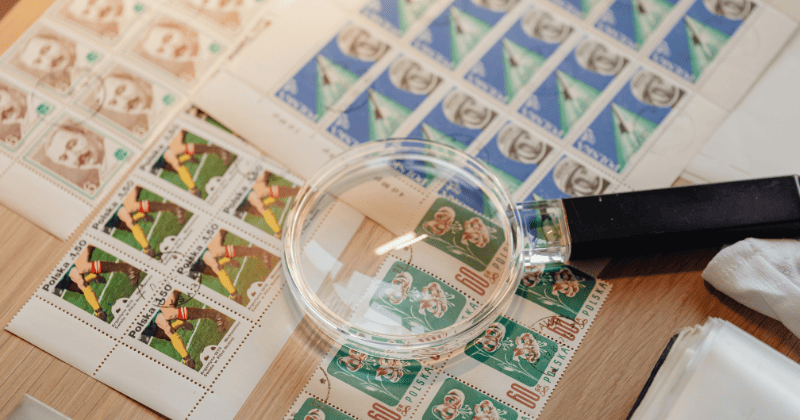はじめに
民事訴訟を提起する際、訴状に収入印紙を貼ることは比較的よく知られていますが、もう一つ、忘れてはならない準備があります。それが「郵便切手(郵券)」の予納です。裁判所は、訴訟が始まると、相手方(被告)に訴状を送ったり、当事者双方に次回の裁判期日を知らせる呼出状を送ったりと、様々な郵便物を発送します。この郵送にかかる費用を、あらかじめ原告に納めてもらうのが「郵便切手の予納」制度です。
「なぜ現金ではなく切手で?」「いくら分、どんな種類の切手を用意すればいいの?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。この手続きは、裁判所ごとにルールが異なり、分かりにくい部分があるのも事実です。
この記事では、裁判手続きの円滑な進行を支える「郵便切手(郵券)」の予納について、その目的から、金額や内訳の調べ方、具体的な提出方法までを解説します。
Q&A:郵便切手(郵券)に関するよくある疑問
Q1. なぜ裁判費用を現金やキャッシュレスで支払うのではなく、わざわざ郵便切手で納めるのですか?
これは、裁判所が郵便物を発送する都度、料金を現金で支払う事務的な手間を省き、効率的に手続きを進めるための実務的な運用です。あらかじめ当事者から切手を預かっておくことで、書記官は必要な郵便物を発送する際に、そこから切手を使って迅速に処理できます。近年、民事訴訟のIT化が進んでいますが、書面の送達など多くの場面で依然として郵便が利用されており、この郵券予納制度が維持されています。
Q2. 予納した切手が訴訟の途中で足りなくなったら、どうなりますか?
訴訟が長引いたり、送達がうまくいかず再送付が増えたりして、予納した切手が不足することがあります。その場合、裁判所の書記官から「郵便切手を追納してください」という連絡があります。指示された金額・内訳の切手を追加で提出(追納)すれば、手続きは問題なく継続されます。この追納を怠ると、必要な送達ができず、訴訟進行に支障が出る可能性があります。
Q3. 訴訟が早く終わった場合、使われずに余った切手は返してもらえますか?
はい、返還されます。訴訟が判決や和解などで終了した時点で、予納された切手に残り(残郵券)がある場合、裁判所の書記官がその残りを計算し、原告に返還してくれます。通常は、裁判所から連絡があるか、判決書などを受け取りに行く際に一緒に返還されることが多いです。
解説:郵便切手(郵券)予納の仕組みと実務
1. 郵便切手(郵券)の予納とは?-裁判のための通信費
郵便切手の予納とは、民事訴訟を提起する原告が、その後の手続きで裁判所が使用する郵便料金に充てるため、あらかじめ一定額の郵便切手を裁判所に納めておく制度です。これは、国の経費で全ての通信費を賄うのではなく、その手続きの利用者である当事者に実費を負担してもらうという「当事者負担の原則」に基づいています。
予納した切手の具体的な使途
予納された切手は、裁判所の書記官によって厳密に管理され、以下のような場面で実際に使用されます。
- 訴状副本と呼出状の送達
訴えが提起されると、まず被告に対して訴状の写し(副本)と第1回口頭弁論期日の呼出状が「特別送達」という特殊な郵便で送られますが、この費用に使われます。 - 期日呼出状の送付
第2回以降の裁判期日が決まった際に、当事者双方に送付されます。 - 準備書面など、相手方提出書面の送付
被告から答弁書や準備書面が提出された場合に、それを原告に送付するために使われます。 - 判決正本の送達
判決が言い渡された後、その判決書を当事者に送達する際にも使われます。
2. 予納郵券の金額と内訳の調べ方
郵便切手の予納で注意すべき点は、その金額や金種(切手の種類)の内訳が、全国の裁判所で統一されていないことです。
【重要】金額は管轄裁判所と当事者の数で決まる
予納する郵券の総額は、訴えを提起する裁判所(地方裁判所か簡易裁判所か、また東京地裁か大阪地裁かなど)によって異なります。さらに、当事者の数(特に被告の人数)によっても変動します。被告が1名増えるごとに、その被告への送達費用として、おおむね2,000円~3,000円程度が加算されるのが一般的です。
- 金額の目安(被告1名の場合)
おおむね6,000円前後(主要な地裁の多くはこの金額です)
各裁判所の予納郵券額を確認する方法
訴状を提出する前には、必ず管轄の裁判所の正確な情報を確認する必要があります。
方法1:裁判所のウェブサイトで確認する
最も簡単な方法です。各裁判所のウェブサイトには、「裁判手続を利用する方へ」といった案内ページがあります。その中の「民事訴訟」や「申立て等で使う書式・定型文」といったコーナーに、「郵便切手一覧表」「予納郵券内訳一覧」などの名称でPDFファイルが掲載されています。
方法2:裁判所に電話で問い合わせる
ウェブサイトで情報が見つからない場合や、被告が多数いるなど事案が複雑な場合は、直接電話で確認するのが確実です。訴状を提出する予定の裁判所の代表番号に電話し、「民事訟廷(みんじしょうてい)担当」または「民事受付係」につないでもらい、「民事訴訟を提起する際の予納郵券の金額と内訳を教えてください」と尋ねます。その際、原告と被告の人数を伝えましょう。
具体例:東京地方裁判所の場合
例えば、東京地方裁判所本庁に訴えを提起する場合(被告1名)、予納郵券額は合計6,000円で、その内訳は以下のように細かく指定されています。
500円×8枚
110円×10枚
100円×5枚
50円×5枚
20円×5枚
10円×5枚
合計:6,000円
このように、裁判所が郵便物を発送する際の様々な料金の組み合わせに対応できるよう、多種多様な金種の切手を求められます。
3. 郵便切手の準備と提出
指定された内訳通りに郵便局で切手を購入し、訴状や収入印紙、添付書類などと一緒に裁判所の受付窓口に提出します。切手は、ばらばらにならないよう、小さな袋に入れたり、A4用紙などに貼り付けたりせず、そのままクリップで束ねて提出するのが一般的です。
弁護士に相談するメリット
郵便切手の予納は、一見すると単純な事務作業ですが、意外と手間がかかり、間違いやすいポイントでもあります。
- 正確な情報調査と準備
弁護士は、事件の管轄裁判所を特定した上で、常に最新の予納郵券情報を正確に把握しています。依頼者は、自分で裁判所のウェブサイトを調べたり、電話をかけたりする手間を省くことができます。 - 煩雑な準備作業の代行
特に都市部の裁判所では、上記で例示したように非常に細かい金種の内訳が求められます。郵便局で多種類の切手を揃えるのは、意外と面倒な作業です。弁護士(または法律事務所のスタッフ)が、これらの準備をすべて代行します。 - ワンストップでの手続き
訴状の作成、添付書類の準備、収入印紙の計算・購入、そして郵便切手の準備まで、訴訟提起に必要な一連の手続きをすべて一括で依頼できます。これにより、依頼者は手続きの全体像を把握しやすくなり、安心して訴訟のスタートを切ることができます。 - 訴訟進行中の管理
訴訟の途中で切手の追納が必要になった場合も、弁護士が裁判所からの連絡を受け、迅速に対応します。また、訴訟終了時の残郵券の還付手続きについても、責任をもって行います。
まとめ
郵便切手(郵券)の予納は、裁判所と当事者間の円滑なコミュニケーションを支え、訴訟をスムーズに進めるために欠かせない、いわば「潤滑油」のような役割を担う手続きです。
その準備におけるポイントは、「訴状を提出する裁判所が指定する、正確な金額と内訳を事前に確認すること」に尽きます。この一手間を惜しむと、手続きの遅れにつながりかねません。
このような事務的な手続きも、紛争解決に向けたプロセスの一部です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、法的な主張の組み立てといった核心部分はもちろんのこと、こうした細かな実務手続きに至るまで、依頼者をサポートいたします。訴訟に関する手続きでご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、様々な分野の法的問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。ご興味をお持ちの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
ご相談はお気軽に|全国対応
長瀬総合法律事務所は、お住まいの地域を気にせず、オンラインでのご相談が可能です。あらゆる問題を解決してきた少数精鋭の所属弁護士とスタッフが、誠意を持って対応いたします。
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス
企業が法的紛争に直面する前に予防策を講じ、企業の発展を支援するためのサポートを提供します。
複数の費用体系をご用意。貴社のニーズに合わせた最適なサポートを提供いたします。