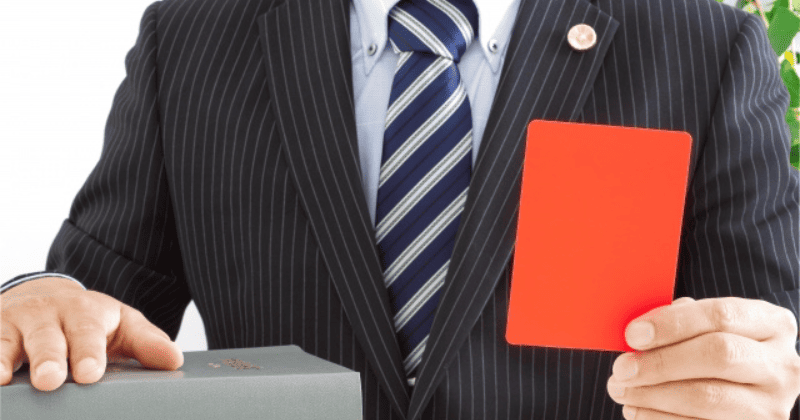はじめに
職場での指導や叱責は、業務を円滑に進め、従業員を育成するうえで不可欠なものです。しかし、厳しい指導が「パワハラ」にあたるかどうかは非常に敏感な問題であり、指導する側とされる側の認識が食い違い、深刻なトラブルを引き起こすケースが多々あります。パワハラ防止法が施行された今、企業としては「正当な業務指導」と「パワハラ」との境界を明確に把握し、従業員への周知や管理職の教育を徹底しなければなりません。
本記事では、職場での言動や指導がどのような場合にパワハラ認定される可能性があるのか、適法な指導と違法なパワハラの境界線、そしてトラブルを防止するポイントなどを解説いたします。
Q&A
Q1. 厳しい叱責も全部パワハラになるのですか?
いいえ。業務上の必要性と合理性が認められる範囲での適切な叱責・指導ならパワハラではなく、正当な業務命令の一環とされます。ただし、人格否定的発言や長時間にわたる罵倒、強迫的言動など「業務上の適正範囲を超える」要素があるとパワハラ認定のリスクが高まります。
Q2. パワハラ防止法では、どのような行為がパワハラと定義されるのでしょうか?
厚生労働省はパワハラを「職場の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、身体的・精神的苦痛を与え、または職場環境を害する行為」と定義しています。具体的には6類型が提示されており、その中の「精神的攻撃」にあたる暴言・侮辱などが本テーマに関連する事例です。
Q3. 部下の勤務態度が悪いので厳しく叱責したら「パワハラだ」と言われました。どうすればいいですか?
まずは叱責した経緯や内容を客観的に整理し、業務上必要な指摘かどうか、言葉遣いや態度が適切だったか検証してください。もし叱責の手法が過度であったなら、謝罪や再指導を行い、部下との認識をすり合わせる。悪質なものではなく正当な指導範囲なら、当事者間の話し合いや上司同席の面談で解決を図るのが望ましいです。
Q4. 「受け手が不快に感じたらパワハラ」という見方もあると聞きます。主観だけでパワハラが成立するのですか?
パワハラの判断では「受け手の主観」は重要な要素ですが、客観的に業務の適正範囲を超えているかが審査されます。つまり、単に「叱責で不快だった」だけでは直ちにパワハラにはならず、行為の態様や内容、時間、場所、頻度など総合的に見て社会通念上許容できないかどうかがポイントです。
Q5. 万が一パワハラと認定されたら、会社にはどんな責任が発生しますか?
会社が対策を怠り、パワハラを放置して被害が拡大すれば、安全配慮義務違反として被害従業員への損害賠償責任が生じる可能性があります。さらに、パワハラ防止法に基づく行政指導や社名公表などもリスクとして考えられます。
解説
パワハラと正当な指導の境界
- 業務上の必要性
指摘や叱責が、明らかに仕事の指導・改善を目的としているか。それとも単なる感情的な攻撃かが大きな区別点。 - 手段・方法の適切性
短時間で的確に課題を指摘し、改善策を伝えるのが正当な指導の範囲。長時間怒鳴り続ける、人格を否定する発言を繰り返すなどはパワハラに該当する恐れが高い。 - 持続的・執拗な行為
一時的な叱責がすべてパワハラになるわけではないが、何度も繰り返し行われ、被害者が精神的に追い詰められるような状況は危険。
典型的なパワハラ言動例
- 人格否定型
「お前は役立たずだ」「生きている価値がない」など極端な侮辱表現。 - 業務外の内容で執拗な攻撃
私生活を嘲笑したり、家族構成を批判するなど業務と無関係な部分で攻撃する。 - 過度の叱責・公開説教
朝礼など多数の前で長時間にわたり叱責し続ける。 - 業務に必要な範囲を超えた命令
露骨に不可能な業務量を与え達成できないと非難する、逆に仕事を与えず暇にさせるなど。
会社が講じるべき防止策
- 就業規則・ハラスメント規程の整備
パワハラの定義や禁止行為、通報窓口、懲戒処分内容を明文化し、全従業員に周知。 - 相談窓口の設置
社内外で複数ルートを設け、被害者が安心して相談できる体制を構築。 - 管理職向け研修
正しい指導方法とパワハラの境界を教える。感情的な叱責や人格否定が違法とされる可能性を認識させる。 - 適正な調査と処分
パワハラ通報があれば迅速に調査。事実が確認されれば加害者に対し懲戒処分を行い、被害者フォローや環境調整も行う。
パワハラ疑いが出たときの流れ
- 相談・通報
被害者または周囲の第三者から「パワハラかもしれない」と申告。 - 初動対応・被害者保護
担当者がヒアリング。加害者と物理的に分離するなど必要に応じて保護措置を実施。 - 事実調査
関係者の聴取、メールや録音などの証拠収集。公正を保つため複数名で調査委員会を設置することも。 - 判定・処分
パワハラ認定の場合、就業規則に基づき懲戒処分。被害者への謝罪や精神面のフォローを行い、再発防止策を実施。
弁護士に相談するメリット
パワハラが疑われる場面では、迅速かつ慎重な対応が必要であり、弁護士に相談すると以下のようなメリットがあります。
- ハラスメント調査の手続き設計
公正な内部調査や第三者委員会の設置方法、被害者・加害者のヒアリング手順などを指導し、後日の裁判リスクを最小化。 - 懲戒処分や就業規則改訂
パワハラ行為が認定された場合の処分を就業規則と整合させ、過度な処分・軽すぎる処分を避けるアドバイス。 - 社内研修サポート
管理職向けのセミナーやパワハラ防止研修の企画支援を行い、企業が法律遵守と予防策を実施できるようサポート。 - 紛争時対応
被害者からの損害賠償請求や労働審判、裁判が発生した際の代理交渉・証拠整理などを包括的に行い、企業リスクを軽減。
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、パワハラ問題に関する多数の実績を活かし、企業のトラブル対応や防止策構築をサポートしています。
まとめ
- 業務上の正当な指導とパワハラの境界は、指導目的や方法、言葉遣いが妥当かどうかにあります。人格否定や執拗な罵倒はパワハラ認定リスクが高いです。
- パワハラ防止法により、企業は相談窓口設置や適切な事後対応などの防止措置を講じる義務があり、違反時には行政指導や社名公表などのリスクがあります。
- 企業は就業規則にパワハラ禁止条項を明確化し、社内研修や懲戒規定の運用ルールを整備することでトラブルを大幅に減らせます。
- 弁護士に相談すれば、調査手続きの適正化や懲戒処分のバランス、紛争対応までトータルで支援を得られ、パワハラ問題による企業ダメージを最小化できます。
企業は管理職や従業員へのパワハラ防止教育を継続し、万一の通報時に即対応できる社内体制を整え、安心して働ける職場環境を維持することが求められます。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
ご相談はお気軽に|全国対応
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス