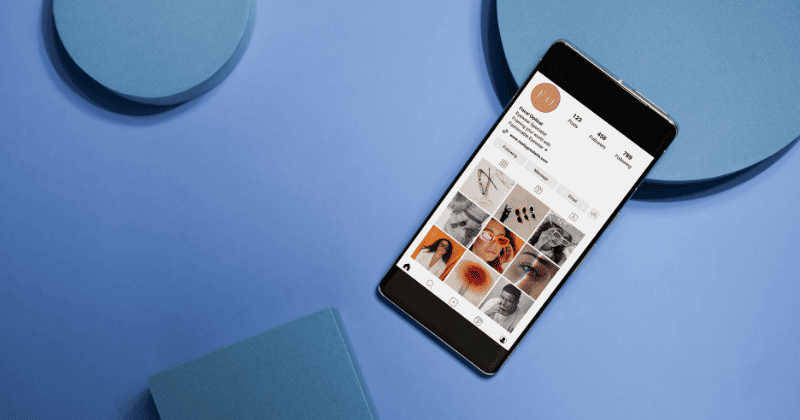はじめに
ネット上で自分や会社に関する誹謗中傷の書き込みを発見したとき、多くの人がまず考えるのは「これを自分自身の手で消すことはできないだろうか?」ということではないでしょうか。弁護士に依頼するには費用もかかるし、手続きも大げさになりそうで、まずは自分でできる範囲で対処したい、と思うのは自然なことです。
結論から言うと、被害者自身がサイト運営者などに削除を依頼し、書き込みを削除してもらうことは可能です。実際に、個人からの依頼で削除に至るケースも存在します。
この記事では、弁護士に依頼する前段階として、ご自身で誹謗中傷の書き込みの削除を依頼するための具体的な方法と、その際に必ず知っておくべき注意点やリスクについて、詳しく解説します。正しい知識を身につけ、状況を悪化させることなく、問題解決への第一歩を踏み出しましょう。
Q&A
Q1. サイトの削除依頼フォームに、怒りに任せて「こんなひどい書き込みは許せない!すぐに消せ!」と感情的に書いて送っても良いですか?
お気持ちお察ししますが、感情的な訴えは避けるべきです。サイト運営者は毎日多くの削除依頼を受けており、感情的な文章では真意が伝わりにくく、スパムとして扱われてしまう可能性すらあります。重要なのは、冷静かつ論理的に、「どの投稿」が、「サイトの利用規約のどの部分に違反しているか」または「あなたのどの権利(名誉権、プライバシー権など)をどのように侵害しているか」を具体的に示すことです。客観的な事実と根拠を伝えることが、削除依頼を成功させるための鍵となります。
Q2. 投稿者のアカウントが分かるので、直接DM(ダイレクトメッセージ)で「書き込みを消してください」とお願いするのは有効な方法ですか?
いいえ、投稿者に直接連絡を取ることは、リスクが高いため、お勧めできません。相手を逆上させてしまい、さらなる誹謗中傷や嫌がらせを誘発する「炎上」の原因になりかねません。また、あなたが反応したことで、相手が警戒して投稿やアカウントを削除し、後の法的措置(投稿者の特定など)に必要となる証拠を隠滅してしまう恐れもあります。相手には接触せず、サイト運営者という第三者を通じて手続きを進めるべきといえます。
Q3. サイト運営者に削除依頼をしたら、「投稿者に意見照会をします」と返事が来ました。これはどういう意味で、投稿はどうなるのでしょうか?
それは、サイト運営者が情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)という法律に基づいた手続きを進めていることを意味します。サイト運営者は、投稿を削除することで投稿者の「表現の自由」を侵害しないよう、投稿者本人に「削除依頼が来ていますが、この投稿の削除に同意しますか?反論はありますか?」と意見を聞くのが一般的です。この「意見照会」に対し、もし投稿者が「削除に反対する」と返信した場合、サイト運営者は中立の立場から投稿を削除しない、という判断を下す可能性が高くなります。
解説
1. 自分で削除依頼をする前に!守るべき3つの原則
ご自身で削除依頼に乗り出す前に、失敗を避け、将来の選択肢を失わないために、必ず以下の3つの原則を守ってください。
原則1:最優先は証拠保全
削除依頼のアクションを起こす前に、必ず証拠を保存してください。問題の書き込みが削除されてしまえば、そもそもどのような権利侵害があったのかを証明することが困難になります。
- 保存すべき内容
誹謗中傷の投稿内容、投稿日時、URL(アドレスバー全体)、投稿者名(ID) - 保存方法
上記の内容が全て一枚に収まるように、PCやスマートフォンのスクリーンショット機能で画面全体を撮影します。印刷して紙で保管しておくことも有効です。
原則2:投稿者への直接連絡はリスクがある
Q&Aでも触れましたが、投稿者本人に直接コンタクトを取るのは百害あって一利なしです。相手を刺激して事態を悪化させるリスクが高いといえます。冷静に、サイト運営者という第三者を通して手続きを進めましょう。
原則3:冷静かつ論理的な主張を心がける
怒りや悲しみをぶつけるのではなく、「削除されるべき法的な理由」を客観的に伝えることが重要です。感情的な訴えは、相手に「面倒なクレーマー」という印象を与え、真摯な対応を妨げる原因になります。
2. 自分でできる削除依頼の具体的な2つの方法
準備が整ったら、以下の方法で削除依頼を試みましょう。
方法1:サイトの「削除依頼フォーム」や「問い合わせ窓口」を利用する
多くのSNSや掲示板、口コミサイトでは、権利侵害や利用規約違反の投稿を報告・削除依頼するための専用フォームを用意しています。
- フォームの探し方
サイトのヘルプセンター、フッター(最下部)にある「お問い合わせ」「サポート」「利用規約」「プライバシーポリシー」などのリンクから探すことができます。 - 一般的な入力項目
- あなたの氏名・連絡先
- 問題の投稿のURLや投稿内容
- 削除を求める理由(権利侵害の種類や、利用規約の違反箇所など)
- 削除理由の書き方のコツ
- (悪い例)「私の悪口が書かれていて不快なので消してください」
- (良い例)「当該投稿は、私の実名を挙げた上で『前科がある』という虚偽の事実を摘示しており、私の社会的評価を著しく低下させるものであるため、名誉毀損(刑法230条)に該当します。また、貴社利用規約〇条の『他者の名誉を毀損する行為』にも違反しています。速やかな削除を求めます」
このように、どの権利が侵害されているか、どの規約に違反しているかを具体的に指摘することで、運営側も判断がしやすくなり、対応してもらえる可能性が高まります。
方法2:サイト運営者の法人情報を調べて、郵送で依頼書を送付する
専用フォームが見当たらない個人ブログや小規模なサイトの場合、運営会社の情報を調べて、郵送で削除依頼書を送る方法があります。
- 運営者情報の探し方
サイトの「会社概要」「運営者情報」「特定商取引法に基づく表記」などのページを確認し、運営会社名と住所を特定します。 - 削除依頼書の作成
特に決まった書式はありませんが、以下の項目を記載した書面を作成します。- タイトル:「削除依頼書」または「送信防止措置依頼書」
- 日付、宛先(サイト運営者名)、差出人(あなたの氏名・住所・連絡先)
- 削除を求める投稿のURL、投稿日時、投稿者名など
- 権利侵害の具体的な内容(上記「良い例」のように、法的根拠・規約違反を明記)
- 「つきましては、本書面到着後7日以内に、本件投稿の削除をお願い申し上げます」といった結びの言葉
- 送付方法
送付した事実と日付を証明できる「内容証明郵便」を利用するのが望ましいです。
- 自分で削除依頼をするときの注意点と限界
ご自身で削除依頼を行う際には、以下の点に注意が必要です。
- 個人情報を開示する場合がある
サイト運営者に対して、あなたが本人であることを示すために、氏名や住所、場合によっては身分証明書のコピーの提出を求められることがあります。 - 無視・拒否されることがある
残念ながら、個人からの削除依頼は、明確な規約違反や権利侵害が認められない限り、無視されたり、「対応できない」と拒否されたりすることが少なくありません。 - あくまで「お願い」ベース
この方法は、法的な強制力を持つものではなく、あくまでサイト側の任意の協力に期待するものです。 - 海外サイトの壁
運営者が海外法人の場合、日本語での依頼が通じなかったり、日本の法律を根拠とした主張を理解してもらえなかったりすることがあります。
弁護士に相談するメリット
ご自身で削除依頼を試みて上手くいかなかった場合や、より確実・安全に削除を目指したい場合は、弁護士への相談を検討しましょう。
- 法的主張による高い説得力
弁護士が代理人として、法律や過去の判例に基づいた専門的な請求書を作成・送付することで、サイト運営者も問題を軽視できなくなり、真摯に対応する可能性が高まります。 - 面倒な手続きの一任
サイトごとの複雑なフォーム入力や、運営者とのやり取り、法的な書面の作成など、時間と手間のかかる作業を全て弁護士に任せることができます。 - 個人情報の安全確保
弁護士が全ての窓口となるため、あなたがご自身の個人情報をサイト運営者に開示する必要がなくなります。安心して手続きを進めることができます。 - 次のステップへのスムーズな移行
もしサイト側が任意の削除請求に応じなかった場合でも、弁護士に依頼していれば、間を置かずに裁判所を通じた削除仮処分などの、より強力な法的措置へスムーズに移行することが可能です。
まとめ
誹謗中傷の書き込みを自分で削除依頼することは、費用をかけずに試せる有効な手段の一つです。専用フォームなどを利用し、「証拠保全」「冷静かつ論理的な主張」といった原則を守って挑戦してみる価値はあります。
しかし、その成功率は決して高いとは言えず、個人情報の開示リスクや、相手にされずに時間だけが過ぎていく可能性も念頭に置かなければなりません。
もし、ご自身で試みてみて「難しい」と感じた場合、あるいは「リスクを冒さず、より確実に問題を解決したい」と強く願うのであれば、それは法律の専門家である弁護士にバトンタッチするタイミングです。
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、ご自身で対応すべきか、弁護士に任せるべきか、といったご相談にも親身に対応いたします。初回相談は無料ですので、一人で悩まず、お気軽にご連絡ください。
長瀬総合の情報管理専門サイト
情報に関するトラブルは、方針決定や手続の選択に複雑かつ高度な専門性が要求されるだけでなく、迅速性が求められます。誹謗中傷対応に傾注する弁護士が、個人・事業者の皆様をサポートし、適切な問題の解決、心理的負担の軽減、事業の発展を支えます。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス
当事務所は多数の誹謗中傷の案件を担当しており、 豊富なノウハウと経験をもとに、企業の皆様に対して、継続的な誹謗中傷対策を提供しており、数多くの企業の顧問をしております。
企業の実情に応じて適宜顧問プランを調整することも可能ですので、お気軽にご連絡ください。