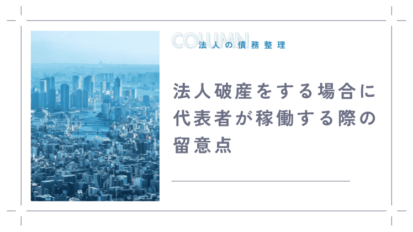はじめに
企業が倒産(破産)に陥るとき、従業員や取引先が損害を被ったと主張して訴訟を提起する可能性があります。未払い賃金を巡る労働訴訟や、背任行為・不正行為による損害賠償請求など、破産が起因となって経営者や役員が法的追及を受けるリスクは決して小さくありません。
本記事では、従業員や取引先からの訴訟リスクに焦点を当て、どのようなケースで訴えられやすいのか、倒産に際して何を注意すべきか、そして適切な対応策を解説します。破産手続で全て解決と思っていると、予期せぬ形で訴訟が始まり、代表者個人の負担が増大してしまうケースもあり得ます。
Q&A
Q1. なぜ破産後に従業員や取引先から訴えられる可能性があるのですか?
破産で会社としての負債は清算されますが、不法行為(故意または重大な過失による損害)や背任行為などがあれば、経営者個人に対し損害賠償請求を行うことが可能です。従業員側のケースでは、未払い賃金や不当解雇の主張があり得ます。取引先は債権を回収できなかった損害を個人に問う場合もあります。
Q2. 会社破産をしたら、未払い賃金はどう処理されるのでしょうか?
未払い賃金は破産財団に十分な資金がなければ全額回収は難しいかもしれません。その結果、従業員が代表者個人の不法行為を主張し、別途賠償請求するケースも考えられます。
Q3. 取引先から「経営者の背任行為で損害を被った」と訴えられるのは、どんなときですか?
例えば、不正な粉飾決算で健全な経営と偽り、取引先に売掛金や追加融資を促した結果、倒産で回収不能となった場合などです。取引先が「経営者は故意に事実を隠していた」と証明すれば、不法行為として賠償義務が認められる可能性があります。
Q4. 訴えられた場合、個人破産で債務は免責されるのでしょうか?
不法行為や故意・重過失による損害賠償債務は、破産法上免責不許可事由に該当する可能性があります。そのため、個人破産をしても免責されないケースがあり、最終的には代表者個人が負担を背負うリスクがあります。
Q5. 訴訟リスクを減らすにはどうすればいいですか?
不正行為や資産隠しを行わないのは当然として、倒産準備段階から弁護士へ相談し、適切な手順で破産手続を行うことが重要です。従業員や取引先とのコミュニケーションを誠実に行い、未払い給与や廃業理由を説明することで、感情的対立を回避しやすくなります。
解説
破産と労働訴訟リスク
- 未払い賃金や解雇トラブル
倒産直前に給与が支払われなかったり、事業終了に伴って従業員が解雇された場合、労働基準法違反や不当解雇を主張する訴訟リスクがあります。破産手続では労働債権が優先されるものの、全額回収できない従業員が代表者個人の不正行為(背任など)を追及するケースも否定できません。 - 労働組合や弁護士の支援
従業員が労働組合や弁護士のサポートを受けると、企業や経営者への対応がより厳格になります。特に代表者が不当解雇や不正行為を行ったとみなされると、破産手続完了後でも損害賠償請求が提起される可能性があります。 - 未払賃金立替払制度
従業員の保護として、未払賃金立替払制度がありますが、一定限度を超える部分は補償されません。
破産と取引先からの訴訟リスク
- 粉飾決算・詐欺的行為
倒産前に粉飾決算で良好な業績を装い、取引先や金融機関から追加融資や多額の信用取引を受けていた場合、破産後に「故意に欺かれた」として損害賠償訴訟を起こされるリスクが高いです。背任行為とみなされる可能性もあります。 - 特定債権者への優先返済(偏頗弁済)
特定の取引先にだけ代金を優先支払いし、他の取引先に損害を与えたと主張されると、詐害行為や不正行為として代表者個人が責任を問われることがあります。- 例:A社とB社が債権者だが、A社にのみ100%支払い、B社は未回収となる…など
- 連鎖倒産による被害主張
取引先が自社の倒産をきっかけに連鎖倒産や大きな損失を被ったとき、「背任行為がなければ連鎖倒産は防げた」などの理屈で責任を追及してくる場合があります。裁判所が認めるかは別問題ですが、訴訟リスクとしては存在します。
訴訟リスクを最小化するための実務ポイント
- 倒産準備段階での誠実な対応
従業員や主要取引先への連絡を隠匿していると、「だまされた」という感情が増幅し、訴訟に発展しやすくなります。早めに事情を説明し、協力を得る努力をすることで感情的対立を緩和し、訴訟リスクを下げられる場合もあります。 - 弁護士の積極活用
倒産が避けられないと判断したら、弁護士を通じて手続きを進めることで、書類作成や債権者対応を適法かつ透明性高く行い、偏頗弁済や不正行為と疑われるリスクを最小化できます。これにより後日の訴訟を防ぎやすくなります。 - 不正行為・資産隠しをしない
資産隠しや粉飾決算などは「免責不許可事由」となるだけでなく、訴訟リスクを大幅に上げます。少しでも疑いを持たれれば徹底追及されるため、絶対に避けることが重要です。 - 和解・示談交渉
訴訟を起こされそうな雰囲気がある場合、示談交渉を事前に進め、分割払いや一定の和解金で合意する道も検討できます。相手方が納得できる説明や謝罪、適切な補償プランを提示できれば、裁判に至らずに済むかもしれません。
弁護士に相談するメリット
- リスク判断と対策立案
弁護士は倒産からくる訴訟リスクを総合的に分析し、どの程度の可能性があるか、どのような事前措置を取ればいいかをアドバイスします。感情的に過剰反応することなく、法的根拠に基づく対策が立てられます。 - 書類・証拠管理の指導
訴訟になると、過去の帳簿や取引記録が重要な証拠になります。弁護士は適正な書類管理を促し、不自然な破棄や改ざんを防ぐことで、背任や不正の疑いを下げるサポートを提供します。 - 示談・和解交渉
訴訟が避けられない状況でも、弁護士が代理で和解交渉を行えば、余計な感情対立を避けながら現実的な解決策を模索しやすくなります。結果として、費用や時間を削減し、双方にとって納得感のある結末を得られる可能性が高まります。 - 裁判対応
万一、訴訟が提起されたら、弁護士が反論の根拠や時効主張、因果関係の否認など適切な法的主張を組み立てて防御します。敗訴しても損害額を軽減できる可能性があり、無用な不利益を回避しやすくなります。
まとめ
従業員や取引先からの訴訟リスクは、倒産・破産によって生じる二次的な問題として見落とされがちですが、実際には経営者にとって大きな負担となり得ます。以下の点を押さえ、リスク管理を徹底しましょう。
- 不正行為や背任行為があると訴訟リスクは上がる
- 未払い賃金や粉飾決算などで損害を受けた従業員・取引先が賠償請求を行うケースがある
- 破産しても不法行為は免責されにくく、個人責任が残る可能性
- 事前に弁護士へ相談し、適切な倒産手続と誠実なコミュニケーションを行う
倒産自体は会社の負債を清算する手続ですが、代表者個人や役員が不正行為や故意の重過失を疑われれば、破産手続後に大きな訴訟リスクを背負うことになります。専門家と連携して、倒産前からリスクを見極め、公正かつ迅速な対処で訴訟リスクを最小限に抑える努力が肝要です。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス