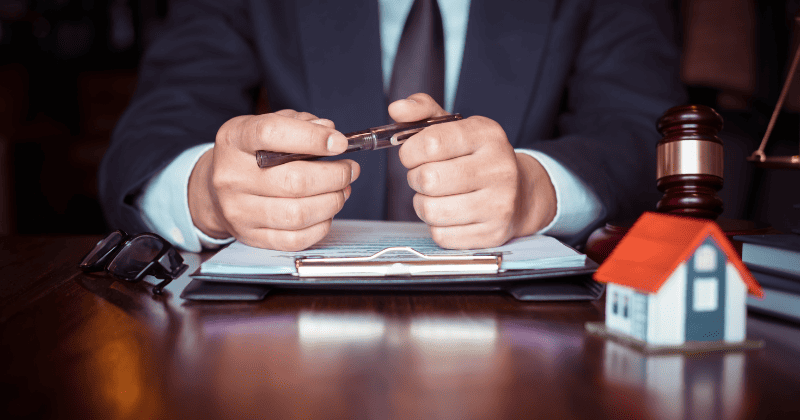はじめに
借地契約の更新や地代増減額、譲渡承諾などをめぐって地主と借地人の交渉が決裂した場合、非訟手続き(ひしょうてつづき)による解決が考えられます。非訟手続きとは、一般的な訴訟(裁判)とは異なり、裁判所が関与しつつ、紛争の解決や法律関係の確認を行う特別手続きです。借地に関しては、地代増減額請求、譲渡・転貸の許可など特定の事項で活用され、紛争を長引かせずに公的な判断を得られるメリットがあります。
本稿では、借地非訟手続きの概要や活用場面、手続きの流れと要件を解説し、地主・借地人が紛争をスムーズに終結させるための一助とします。
Q&A
Q1.借地非訟手続きとは何ですか?
借地非訟手続きとは、借地借家法に基づき、裁判所が司法判断(判決)ではなく、許可・決定の形で関与する特別な手続きです。代表的な非訟手続きとして、
- 借地条件変更申立事件(借地借家法第17条第)
- 土地の賃借権譲渡または転貸の許可申立事件(借地借家法第19条第)
- 借地権設定者の建物及び土地賃借権譲受申立事件(借地借家法第19条)
などがあります。通常の訴訟とは異なり、当事者間の紛争に公的な調整を加え、迅速・円満に関係を確定させる狙いがあります。
Q2.非訟手続きと調停・訴訟の違いは何でしょうか?
- 非訟手続き
当事者の利害対立があるものの、訴訟のように勝敗を決めるのではなく、裁判所が決定を行う形式。 - 調停
簡易裁判所や家庭裁判所で行われる話し合いの手続き。合意すれば調停調書が作成され、裁判上の和解と同じ効力。 - 訴訟(裁判)
原告と被告に分かれて争点を審理し、最終的に判決で勝敗が決まる形式。
Q3.手続きの流れはどのようになっていますか?
一般的に以下の流れで進みます。
- 申立書の提出
申立人が、管轄裁判所(借地物件の所在地など)に必要書類を提出。 - 裁判所での審理
当事者や利害関係人の意見を聞き、必要に応じて鑑定や調査を行う。 - 調整・意見聴取
裁判所は紛争解決のために利害を調整し、和解的な解決を目指す場合がある。 - 許可・決定
最終的に裁判所が「許可」「不許可」「増額・減額率」などの決定を下す。これは判決ではなく非訟手続き特有の処分。
Q4.弁護士に相談する意義は何でしょうか?
借地非訟手続きは一般的な民事訴訟に比べてルールや運用が特殊であり、法律知識と実務経験が不可欠です。弁護士が関与すると、
- 申立書・書面作成
要点を的確に整理し、法律的根拠を明確化して提出することで、裁判所の理解を得やすい。 - 証拠や鑑定人の手配
地代増減額で不動産鑑定士の意見書が必要な場合、弁護士が適切にコーディネート。 - 地主・借地人双方の利害調整
和解的な解決を志向する非訟手続きでは、弁護士の交渉力が紛争の早期解決につながる。
解説
借地非訟手続きの主な種類
- 借地権譲渡・転貸許可の非訟手続き
借地人が第三者へ権利を譲渡または転貸したいが、地主が承諾しない場合の救済手段。 - その他
- 借家に関する非訟手続きもあるが、本稿では借地に限定。
- 更新拒絶に関するトラブルは非訟手続きではなく調停・訴訟になることが多い。
非訟手続きの特徴
- 判決ではなく“決定”
非訟事件では、裁判所の結論は“判決”ではなく“決定”の形を取る。 - 迅速性
通常訴訟に比べ、非訟手続きはやや簡易・迅速な解決を志向する制度。ただし事案が複雑な場合は時間がかかることも。
実務上の流れ(譲渡許可申立の例)
- 申立書作成・提出
- 借地人が「地主が譲渡に承諾しないため、裁判所の許可を求める」旨を申立。
- 物件概要、現在の契約内容、譲渡先の情報、譲渡理由などを記載。
- 裁判所での審理
- 裁判所が地主や借地人、譲受人候補などから意見聴取。
- 必要に応じて書面・鑑定書を提出させ、承諾料の妥当性や地主の不利益を判断。
- 決定
- 裁判所が「譲渡を許可」または「不許可」を判断。
- 許可決定が出れば、地主の承諾がなくても譲渡有効になる(借地借家法第19条)。
- 不服申し立て
- 当事者が裁判所の決定に不服なら、即時抗告などの方法で上級審へ移行する場合あり。
弁護士に相談するメリット
- 申立書・必要書類の適切な作成
非訟手続きは要件を満たす書類がそろっていないと却下や不備指摘を受ける恐れ。弁護士が書式・内容を整え、スムーズな進行をサポート。 - 紛争リスクの軽減
地主・借地人の感情的対立が激化しがちなケースで、弁護士が客観的立場から交渉し、和解案を提示。裁判所決定前の早期解決を目指す。 - 専門知識の活用
建物評価等には不動産鑑定士の意見が欠かせない場面があり、弁護士が鑑定士との連携をコーディネートし論点を整理。
まとめ
借地非訟手続きは、地主と借地人の紛争を「訴訟」ではなく「許可・決定」の形で解決する制度。
活用例
借地権譲渡・転貸許可申立
地主承諾が得られない際に、裁判所に許可を求める。
特徴
判決で勝敗を決めるのではなく、裁判所が最適な調整を行う柔軟な手続き。
弁護士活用
書面作成、専門家連携、紛争防止、早期円満解決を期待できる。
借地非訟手続きは地主・借地人双方にとって解決までの時間やコストを抑えながら、適正な裁判所の関与を得られる利点があります。ただし、書面や主張の組み立てが複雑になる場合が多く、弁護士などの専門家との連携がポイントです。
長瀬総合の不動産専門サイト
不動産トラブルは、法務や税務だけでなく、不動産評価の問題等が関わる、複雑かつ高度な専門性が要求される問題です。不動産売買、賃貸、相続、共有問題等に悩む不動産会社・オーナーの皆様をサポートし、適切な問題の解決、紛争の予防、事業の発展を支えます。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス