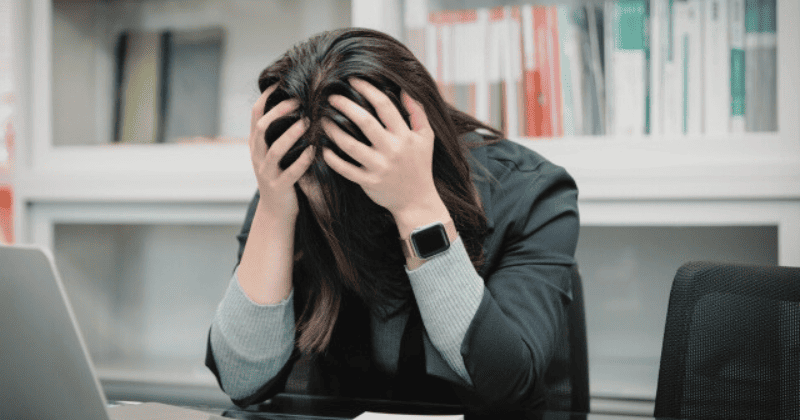はじめに
職場におけるメンタルヘルス対策は、従業員の健康管理だけでなく、企業の生産性向上やリスク管理にも直結する重要なテーマです。長時間労働や人間関係のトラブルなどが原因で、うつ病などの精神疾患を発症する従業員が増えると、休職や離職につながり、企業側にも大きな負担が生じます。
また、2015年の労働安全衛生法改正で義務化されたストレスチェック制度は、メンタル不調を早期発見し、労働者が自身のストレス状態を把握できる仕組みとして注目されています。本記事では、メンタルヘルス対策における産業医の役割や、企業が取るべき具体策、法的留意点などを弁護士法人長瀬総合法律事務所が解説します。
Q&A
Q1:ストレスチェックは全員受けさせなければならないのですか?
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、年1回のストレスチェックが義務とされています。ただし、受検は労働者の任意のため、強制はできません。企業としては受検を促すことはできますが、受検拒否を理由に不利益な扱いをするのは違法となる可能性があります。
Q2:産業医の選任はどのような場合に必要ですか?
労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者がいる事業場に産業医を選任することが義務付けられています。産業医は従業員の健康管理や作業環境の改善、健康診断の実施や面談指導などを行う専門家として重要な役割を担います。企業規模や業種によっては衛生管理者や安全管理者などの選任義務も生じる点に留意が必要です。
Q3:メンタル不調の従業員が休職から復職する際、企業が注意すべきポイントは?
復職時には、本人の主治医や産業医の意見を参考にしながら、段階的な業務復帰を検討することが望ましいといえます。いきなりフルタイム勤務に戻すと再発リスクが高まるため、短時間勤務や業務量の調整など配慮を行います。また、ハラスメント対策や職場環境の改善が不十分だと、再度メンタル不調が生じるリスクが高くなるので注意が必要です。
Q4:従業員がメンタル不調を理由に長期休職したまま復職時期が見えない場合、解雇できますか?
メンタルヘルスによる休職の場合でも、「業務に復帰できる見込みが全くない」「休職期間を十分に設定しても回復せず、社会通念上解雇せざるを得ない」といった厳格な要件を満たさない限り、安易な解雇は不当解雇とみなされるリスクが高いといえます。解雇を検討する際は休職規程に定める休職期間を経過したか、産業医や主治医の意見を踏まえた回復見込みがないかどうかなどを慎重に判断しましょう。
解説
メンタルヘルス対策の重要性
- 従業員の健康と企業リスクの防止
- メンタル不調の予防・早期対応が遅れると、従業員の休職や離職につながり、人材流出・生産性低下を招きます。
- 過労や上司のパワハラが原因のうつ病で従業員が自殺した場合、企業は安全配慮義務違反として高額な損害賠償を命じられるリスクがあります。
- 職場環境改善によるメリット
- メンタルヘルスを重視する企業は、従業員のエンゲージメントが高まり、離職率の低減や組織の活性化が期待できます。
- 風通しが良く、相談しやすい職場文化を育むことで、早期にトラブルを発見・解決する土壌が形成されます。
ストレスチェック制度の概要
- 対象と実施フロー
- 常時50人以上の事業場で義務化。従業員に対するアンケート方式(心理的負担の程度を図る調査)を年1回実施し、本人がストレス度合いを把握できるようにします。
- 高ストレス者が希望した場合、医師による面接指導を行い、必要に応じて就業上の措置(配置転換、労働時間短縮など)を検討します。
- 結果の取り扱いとプライバシー保護
- ストレスチェック結果は産業医や外部の実施機関が集計・分析し、事業者が個人結果を把握することは原則できません(本人が同意した場合を除く)。
- 高ストレス者を特定して企業が一方的に査定などに使うことは禁じられており、プライバシー保護が厳格に求められます。
- 職場改善への活用
- 組織単位での集計データ(職場ごとのストレスレベル)を産業医や衛生委員会が分析し、職場環境の改善策を検討することが推奨されています。
- 単なるチェックにとどまらず、実質的な改善アクションにつなげることが制度の主目的です。
産業医の役割と連携
- 産業医の主な業務
- 健康診断の実施・結果評価
- ストレスチェック結果の分析と高ストレス者への面談実施
- 作業環境の巡視と改善提案
- メンタル不調者の復職判定・配置転換などのアドバイス
- 企業内の体制づくり
- 産業医は単に「健康診断をやるだけ」の存在ではなく、衛生委員会や人事部門、管理職と連携しながら従業員の健康管理をトータルでサポートします。
- 定期的な情報共有の場(産業医面談のフィードバック、職場巡視結果の報告など)を設け、経営層も含めたコミュニケーションを図ることで、実効性の高いメンタルヘルス対策を実現します。
- 外部リソースの活用
- 企業規模や業種によっては、専属産業医の配置が難しい場合があります。その際は「嘱託産業医」や「産業保健総合支援センター」などの外部機関を活用する選択肢があります。
- メンタルヘルス専門のカウンセラーやEAP(従業員支援プログラム)サービスを導入し、産業医と併せて従業員の相談体制を整える企業も増えています。
弁護士に相談するメリット
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、職場のメンタルヘルス対策や産業医との連携に関して、以下のようなサポートを行っています。
- 就業規則・休職規程の整備
- メンタルヘルス不調時の休職制度、復職手続き、ハラスメント防止策などを最新の法令・判例に基づき整備し、トラブルを未然に防ぎます。
- 産業医や産業保健スタッフとの連携方法を明文化し、企業・従業員双方が安心して相談できる環境づくりをサポートします。
- メンタルヘルス不調者対応のアドバイス
- 休職・復職の要件や期間延長、配置転換などの具体的な措置を行う際に、労働法上のリスクを点検し、適切な手続きを指導します。
- 不当解雇や安全配慮義務違反が疑われる事態にならないよう、社内ドキュメントや面談記録の整備をサポートします。
- ハラスメント対策と訴訟対応
- パワハラやセクハラが原因でメンタル不調が生じた場合、企業の安全配慮義務が問われることがあります。弁護士が事前にハラスメント防止規程の作成や社員研修をサポートします。
- 万が一、従業員や遺族から損害賠償請求があった場合でも、労働審判や訴訟手続きを迅速に対応し、企業の立場を適切に主張立証します。
- ストレスチェック制度の運用アドバイス
- ストレスチェックの実施体制や結果のフィードバック方法、プライバシー保護の仕組みなどを法的観点で点検し、適正な運用を行うための指針を提供します。
- 組織分析結果を活かした職場環境改善策への落とし込みや、産業医との協議の進め方についてもサポートします。
まとめ
- 職場のメンタルヘルス対策は、従業員の健康保護だけでなく、企業リスクの回避や生産性向上にも直結する重要なテーマ。
- ストレスチェック制度や産業医の活用により、メンタル不調の早期発見・早期対応が期待できるが、実効性を高めるには企業内体制や就業規則の整備が不可欠。
- 従業員が休職から復職する際は、段階的な業務復帰や職場環境調整が重要で、無理解な対応は再発を招くリスクが高い。
- 弁護士と連携し、ハラスメント防止や休職・復職手続きの適正化などを図ることで、企業は安心してメンタルヘルス対策を推進できる。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
ご相談はお気軽に|全国対応
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス