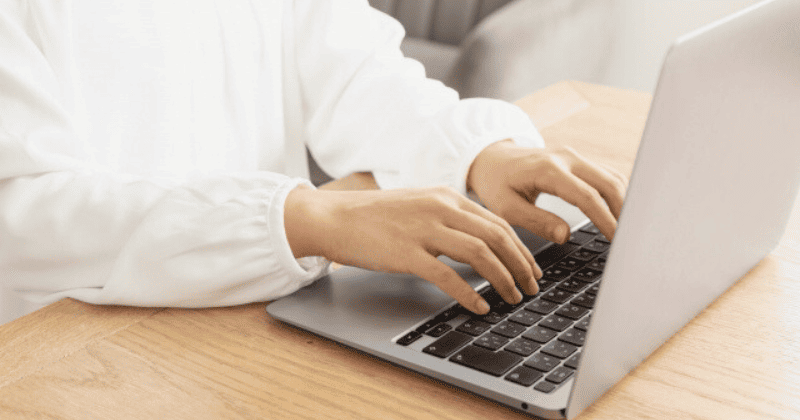はじめに
近年、働き方改革やデジタル技術の進展により、副業・兼業を容認・推進する企業が増えています。従業員が本業以外の収入源を得ることで、個人のスキルアップやモチベーション向上につながるほか、企業側としても多様な人材を確保しつつイノベーションを促すメリットが期待できます。
一方で、労働時間管理や競業避止義務、情報漏えいなどのリスクを適切に管理しなければ、副業・兼業をめぐるトラブルに発展する可能性があります。本記事では、副業・兼業を推進するうえで企業が押さえるべき法的留意点や就業規則の整備ポイントを、弁護士法人長瀬総合法律事務所がわかりやすく解説します。
Q&A
Q1:企業は従業員の副業・兼業を禁止できますか?
結論として、合理的な理由があれば副業・兼業を制限することは可能です。たとえば、「企業秘密の漏えいリスクが高い業務」「本業に支障が出るような過重労働」「競合他社での勤務」などが挙げられます。ただし、国の方針としては副業・兼業を推進する流れにあり、無制限に禁止するのは難しくなってきています。企業は就業規則に明示し、具体的な禁止・制限の根拠を示すことが重要です。
Q2:副業・兼業で発生する労働時間はどのように管理するのでしょうか?
労働基準法上、複数の事業所で働く場合でも、通算の労働時間が法定労働時間の上限(1日8時間、週40時間)を超えれば割増賃金の問題が発生する可能性があります。ただし、現実には別々の企業がそれぞれ労働時間を把握するのは困難です。現行法では副業先の労働時間を含めた「総労働時間」を一元管理する仕組みは明確に定められていませんが、行政のガイドラインでは自己申告制や相互情報共有によって過重労働を防ぐよう求められています。
Q3:競合他社での副業を禁止したい場合、どうすればよいですか?
就業規則や労働契約書で競業避止義務を明記し、具体的にどのような業務形態や取引先との関係を禁じるか定めます。ただし、過度に広範・長期間にわたる競業避止義務は無効とされる可能性があります。実際には、「類似の商品・サービスを扱う会社での勤務を禁止」「顧客リストや営業ノウハウの利用を禁止」など、合理的な範囲に絞って規定することが望ましいです。
Q4:副業で成果を上げた従業員が本業での昇進や評価に影響を与えることはありますか?
法的な規制はありませんが、企業の評価制度によっては、副業の成果やスキルがプラスに働く場合があります。逆に、副業に時間を割きすぎて本業のパフォーマンスが下がれば、評価にマイナスの影響が及ぶ可能性もあります。企業は評価基準を明確にし、副業・兼業の実績をどのように本業の評価に反映させるか、あらかじめ取り決めておくことが望ましいでしょう。
解説
副業・兼業解禁の背景
- 働き方改革の推進
- 国による「働き方改革実行計画」で、副業・兼業が推奨されています。スキルを持つ人材の多様な活躍が期待されている一方、過重労働や情報漏えいリスクへの対応が課題となっています。
- 企業メリット
- 副業・兼業を認めることで、従業員が外部の知見を得て本業に還元する「スキルアップ効果」が見込めます。
- 従業員満足度の向上や人材流出の防止にも寄与し、リクルーティング面でも「副業OK」という柔軟性はアピールポイントとなります。
- 注意すべきデメリット
- 長時間労働につながり、過労や健康障害のリスクが高まる可能性があります。
- 競合他社への情報流出、会社の信用を失墜させるような言動(SNS発信など)が起きる可能性もあり、企業は適切に規律を保つ仕組みを整える必要があります。
就業規則整備のポイント
- 副業・兼業に関する基本方針
- 「原則自由だが、業務上の支障や秘密保持を害する行為は禁ずる」「事前届出制を採用する」など、企業が望む運用方針を明確に記載します。
- 副業・兼業をどの範囲で認めるか、業種や時間帯、収入範囲など細かい基準を定める場合もあります。
- 事前届出・許可制の導入
- 副業・兼業をする従業員に対して、事前に企業へ届け出る義務を課すことで、リスクを事前把握できます。
- 許可制にする場合は、却下・取り消しの基準も就業規則に定めておき、従業員が納得しやすいプロセスを整えることが望ましいといえます。
- 競業避止義務・秘密保持義務
- 企業固有のノウハウや顧客情報が流出しないように、競合他社での勤務や取引先との利害関係が生じる副業を制限する条項を設けます。
- 違反時の懲戒処分内容も明示し、違反行為の重大性を周知しておきましょう。
- 健康管理・過重労働対策
- 副業による疲労が蓄積し、本業に支障をきたすことがないよう、労働時間の通算管理や健康診断の実施などをどのように行うか定めます。
- 自己申告制をベースにした残業時間チェックの仕組みが求められますが、従業員にも協力義務を持たせることが重要です。
実務上の注意点と事例
- 情報漏えい対策
- ITリテラシーやコンプライアンス研修を実施し、副業先での情報取り扱いに関する注意点を周知します。
- 契約書面やNDA(秘密保持契約)で明確に禁止事項を定めるケースもあるため、従業員が誤って企業秘密を漏らさないよう徹底指導が必要です。
- SNSや副業サービスでのトラブル
- 副業の種類によっては、SNSやネットを活用したビジネスがあり、企業の名誉・信用に悪影響を及ぼす投稿や発言が問題になることがあります。
- 就業規則で「SNS利用ガイドライン」を設定し、会社の名誉毀損や混同を招く行為を明確に禁止することが効果的です。
- 副業先の労災・保険関係
- 副業先で発生した労災は、原則として副業先が労災保険を適用します。ただし、通勤経路や作業内容によっては本業との複合的な責任問題が生じる可能性もあり、トラブル回避のために従業員が保険加入状況を確認しておくべきです。
- 社会保険の二重加入問題などは通常起きませんが、国民健康保険・国民年金の場合には副業先の収入申告が関連するため、従業員に注意喚起が必要です。
- 副業の成果物の権利帰属
- 副業で作成したコンテンツや発明などの権利関係をめぐって、本業との区別が曖昧になるケースがあります。たとえば、本業の業務時間や設備を利用して作成した場合、企業が権利を主張する余地があるかもしれません。
- 「職務発明」や「著作権」の帰属について、事前にルールを明確化することで紛争を予防できます。
弁護士に相談するメリット
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、副業・兼業をめぐる企業のリスク管理と制度設計について、以下のようなサポートを提供しています。
- 就業規則・副業規程の整備
- 副業容認の基本方針や届出制度、競業避止義務・秘密保持義務の設定など、企業の実態に合わせた規程作りを支援します。
- 同時に、労働基準法やその他法令との整合性をチェックし、法的リスクを最小化します。
- 競業避止義務・秘密保持契約のレビュー
- 個別の労働契約書やNDAに定める競業避止条項が、裁判所で有効と認められるための要件を満たしているかを点検。
- 過度に広範な制限が無効とされないよう、バランスの取れた文言を提案します。
- トラブル発生時の対応・交渉
- 従業員が無断で競合他社に就職していた、企業秘密を流用して副業で利益を上げていた、SNSで会社の信用を害する行為をしていたなどのトラブル発生時に、事実調査や懲戒手続きの適正化をサポート。
- 必要に応じて労働審判や訴訟対応も行い、企業の利益保護を図ります。
- 健康管理や労働時間通算の助言
- 副業を認める場合の残業代対応や労働時間管理ルールを検討し、過重労働のリスクを低減するためのアドバイスを行います。
- 自己申告制の活用法や従業員教育のポイントを提案し、企業の安全配慮義務を果たせる体制を構築します。
まとめ
- 副業・兼業は従業員のスキルアップや企業の魅力向上に役立つ一方、競業避止や労働時間管理、秘密保持などの課題をクリアしなければ、トラブルの温床となる可能性が高い。
- 企業がリスクを最小限に抑えながら副業・兼業を推進するには、就業規則の整備や届出制度、合理的な禁止・制限規定などの明確化が不可欠。
- 健康管理や長時間労働に関する対策、SNS・情報漏えいに対するルール整備も重要な要素となる。
- 弁護士をはじめとする専門家のアドバイスを受けながら、制度設計と運用を進めることで、労使双方にメリットのある多様な働き方を実現できる。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
ご相談はお気軽に|全国対応
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス