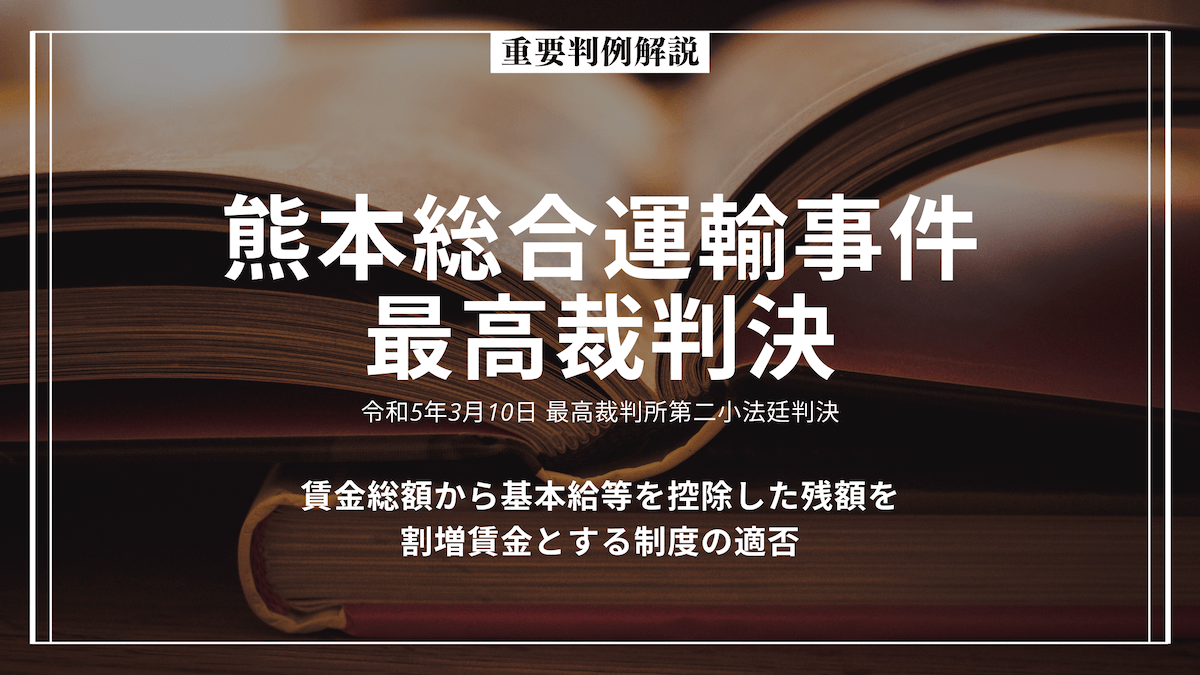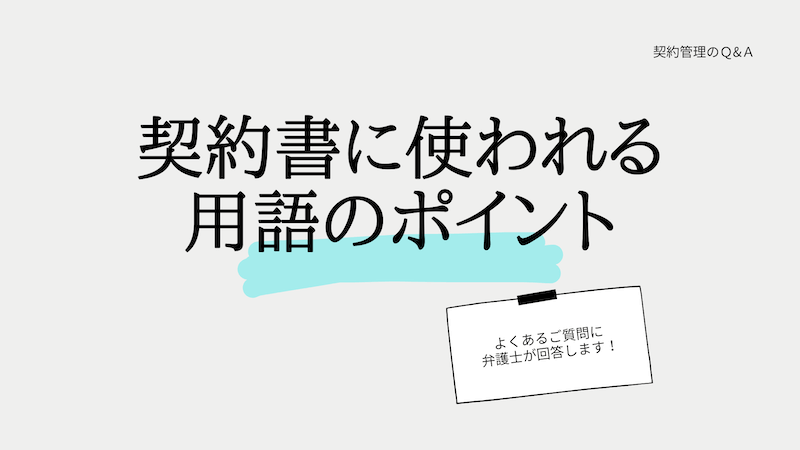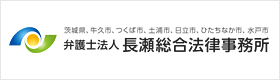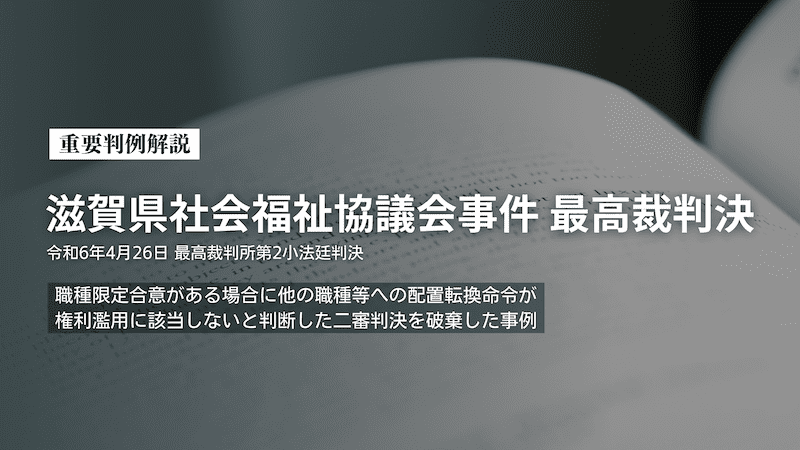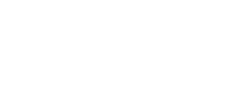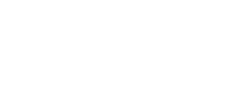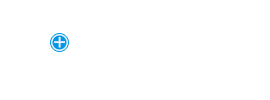最高裁判所第三小法廷判決令和2年10月13日)(令和元年(受)第1190号、第1191号 損害賠償等請求事件)〜同一労働同一賃金における「退職金」の待遇差に関する判断要素〜
解説動画
2020年11月13日(金)に開催されたセミナー動画です。
はじめに 本稿の趣旨
令和2年10月13日、無期雇用である正社員に対して賞与を支給する一方、有期雇用である契約社員に対して退職金を支給しないことが、不合理な待遇差であり労働契約法20条に違反するかどうかが争点となった裁判において、最高裁判決が下されました(最高裁判所第三小法廷判決令和2年10月13日[1])(令和元年(受)第1190号、第1191号 損害賠償等請求事件)(以下、本稿では「本件最高裁判決」と記載します)。
本件最高裁判決の前審であるメトロコマース事件(第2審)東京高判平成31年2月20日(以下「本件高裁判決」と記載します。)は、有期契約社員への退職金の不支給が不合理な待遇差であり、少なくとも正社員の4分の1に相当する額すら支給しないことは、労働契約法20条に違反すると判断しました。本件高裁判決が、有期契約社員に対する退職金の不支給が違法であり、少なくとも正社員の4分の1に相当する金額を支払う必要があると判断したことは、大きな衝撃をもって紹介されました。本件高裁判決は、初めて退職金の不支給が不合理な待遇差であると判断したこともあり、同一労働同一賃金の人事労務管理に与えるインパクトの大きさを象徴するものであったといえます。
無期契約社員に対しては退職金を支給する一方、有期契約社員に対しては退職金を支給しないという待遇差を設定する企業は決して少なくありません。
このような状況において、本件高裁判決が退職金の不支給を違法と判断した一方、本件最高裁判決も本件高裁判決の判断を維持するのかどうかは、非常に関心をもって注目されていました。
しかしながら、本件最高裁判決は、本件高裁判決の判断を覆し、有期契約社員に対し退職金を支給しないことは、不合理な待遇差にはあたらず、労働契約法20条には違反しないという判断を示しました。
国は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)(以下「無期契約労働者」と記載します。)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)(以下「有期契約労働者」と記載します。)の間の不合理な待遇差の解消を目指す同一労働同一賃金を導入し、2020年4月1日より大企業を対象に短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「パート有期法」と記載します。)を施行しました。
しかしながら、具体的に同一労働同一賃金の考え方において、どのような待遇差であれば合理性があるといえるのか、未だ明確になっているとは言い難い状況です。
本稿では、本件の事実関係の概要を整理するとともに、本件最高裁判決が与える実務上の影響について考察したいと思います。なお、本稿の内容は、あくまでも筆者の一考察に過ぎないことにご留意ください。
労働契約法20条の規制内容及び同一労働同一賃金ガイドラインの考え方
労働契約法20条の規制内容
本件最高裁判決を検討する前提として、労働契約法20条の規制内容について説明します。
労働契約法20条は、「有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。」と規定しています。
労働契約法20条は、同一の使用者に雇用されている有期契約労働者と無期契約労働者について、「期間の定めがあること」によって両者の労働条件に相違がある場合、①職務の内容、②当該職務の内容及び配置の変更の範囲並びに③その他の事情を考慮して、その相違が「不合理」なものであることを禁止した規定といえます。③その他の事情とは、「有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が不合理と認められるものであるか否かを判断する際に考慮されることとなる事情は、労働者の職務内容及び変更範囲並びにこれらに関連する事情に限定されるものではない」と判示されているように(長澤運輸事件最判平成30年6月1日)、広く諸事情が考慮されるものと解されます。
労働契約法20条は、「均衡待遇規定(不合理な待遇差の禁止)」であるといわれますが、かかる規定内容は、改正後のパート有期法第8条においても基本的に変わるものではないと解されます。
同一労働同一賃金ガイドラインの考え方
かかる労働契約法20条の解釈を明らかにした長澤運輸事件最判平成30年6月1日及びハマキョウレックス事件最判平成30年6月1日を踏まえ、国は、平成30年12月28日、「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」(以下「同一労働同一賃金ガイドライン」といいます。)[2]を公表し、同一労働同一賃金に関する基本的な考え方及び各手当に関する考え方を例示しました。
もっとも、同一労働同一賃金ガイドラインにおいても、「事業主が、第3から第5までに記載された原則となる考え方等に反した場合、当該待遇の相違が不合理と認められる等の可能性がある。」と記載されているように、同一労働同一賃金ガイドラインのみでは、無期契約労働者と有期契約労働者との間の待遇差が直ちに違法とまでは断言できるわけではなく、待遇の相違が不合理といえるかどうかは、個別のケースによって判断されることになります。
したがって、同一労働同一賃金ガイドラインだけでは、無期契約労働者と有期契約労働者との間の賞与に関する待遇差が合理性を有するといえるかどうかは判断できない場合があることに留意する必要があります。
同一労働同一賃金ガイドラインにおける退職金の扱い
また、同一労働同一賃金ガイドラインでは、退職金に関する考え方は提示されていません。もっとも、同ガイドラインには、「なお、この指針に原則となる考え方が示されていない退職手当、住宅手当、家族手当等の待遇や、具体例に該当しない場合についても、不合理と認められる待遇の相違の解消等が求められる。」と記載されているとおり、退職金に関しても、同一労働同一賃金の考え方は妥当し、不合理な待遇差の解消が求められることには変わりません。
本件最高裁判決の概要
以下では、退職金に関する正社員と有期契約社員との間の待遇差が労働契約法20条に違反しないと判断した本件最高裁判決の概要及び判断理由について解説します。
事案の概要
本件は、東京メトロと有期労働契約を締結していた契約社員が、無期労働契約を締結している正社員との間で、退職金等に相違があったことは、労働契約法20条に違反するものであったとして、東京メトロに対し、不法行為に基づき、上記相違に係る退職金相当額等の損害賠償を求めた事案です。
事実関係等の概要
東京メトロにおける社員の区分
東京メトロでは、従業員は、①無期雇用の正社員、②有期雇用の契約社員A(後に無期労働契約の「職種限定社員」に変更)、③有期雇用の契約社員B、の3つの類型に分かれていました。第1審原告らは、③契約社員Bに該当します。
①正社員、②契約社員A、③契約社員Bの労働条件等を整理すると、以下の一覧表のようになります。
| 労働条件 | 正社員 | 契約社員A (職種限定社員) |
契約社員B 第1審原告ら |
|
|---|---|---|---|---|
| 身分 | 雇用期間 | 無期 | 有期 契約社員Bのキャリアアップの雇用形態 平成28年4月、「職種限定社員」に改められ、無期労働契約に変更 |
有期 |
| 定年 | 65歳 | 65歳 | 65歳 | |
| 就業規則 | あり(正社員用) | あり(契約社員A用) | あり(契約社員B用) | |
| 就業場所 | 限定なし | 本社の施設課、メトロス事業所、ストア・ショップ事業所以外には配置されていない | リテール事業本部メトロス事業所管轄METROS売店 | |
| 勤務内容 | 限定なし | 売店の販売業務 | 売店の販売業務限定 | |
| 基準賃金 | 本給 | 職務給+年齢給 | 月給制 | 1年目時給1020円 毎年10円ずつ昇給 |
| 基準外賃金 | 賞与 | 夏冬にそれぞれ本給2ヶ月分 + 一定額(17万円または17万6000円など) |
年2回 年額59万4000円 初年度年額44万7000円 経営状況による特別手当あり |
夏冬に各12万円 |
| 退職金 | 勤続年数に応じる(10年で242万円) | なし ただし平成28年4月以降、認められる |
なし | |
正社員と契約社員Bの職務内容・変更の範囲
次に、東京メトロにおける正社員と契約社員Bの職務内容及び変更の範囲を整理すると、以下のようになります。
| 労働条件 | 正社員 | 契約社員B 第1審原告ら |
|
|---|---|---|---|
| 身分 | 雇用期間 | 無期 | 有期 |
| 定年 | 65歳 | 65歳 | |
| 就業規則 | あり(正社員用) | あり(契約社員B用) | |
| 売店業務従事者数 | 18名 (全体で約600名) |
78名 | |
| 労働時間 | 本社 1日7時間40分 週38時間20分 販売員 1日7時間50分 週39時間10分 |
個別契約だが多くは以下のとおり 1日8時間 週40時間 又は 1日7時間(土のみ5時間) 週40時間 |
|
| 就業場所 | 限定なし | リテール事業本部メトロス事業所管轄METROS売店 | |
| 勤務内容 | 限定なし | 売店の販売業務限定 | |
| 基準賃金 | 本給 | 職務給+年齢給 | 1年目時給1020円 毎年10円ずつ昇給 |
| 資格手当又は 成果手当 |
L-3以上に支給 | なし | |
| 早番手当 | なし | 1回につき150〜300円 | |
| 皆勤手当 | なし | 月額3000円 | |
| 住宅手当 | 扶養あり:15,900円 扶養なし:9200円 |
なし | |
| 家族手当 | 扶養1人で8000円 2人目以降4000円 |
なし | |
| 基準外賃金 | 賞与 | 夏冬にそれぞれ本給2ヶ月分+一定額(17万円または17万6000円など) | 夏冬に各12万円 |
| 年末年始出勤手当 | 日勤4000円、長日勤6000円、宿泊・長日勤8000円 | 3500円→4000円 | |
| 深夜労働手当 | 3割5分増 | 2割5分増 | |
| 早出残業手当 | 2時間まで:2割7分増 2時間超:3割5分増 |
2割5分増 | |
| 休日労働手当 | 3割5分増 | 3割5分増 | |
| 代休手当 | 代休19日または2割5分増の代休手当 | なし | |
| 退職金 | 勤続年数に応じる(10年で242万円) | なし | |
| 褒賞 | 永続勤労についてのみ相違 勤続10年時に表彰状+3万円、以後勤続10年毎に同じく褒賞の定めがある 定年退職時に感謝状+5万円相当の記念品 |
永続勤労褒賞はなし その他の褒賞は正社員に同じ |
|
本件の争点
本件では、正社員と第1審原告との間における、退職金等の待遇差が、労働契約法20条に違反するかどうかが争点となりました。
なお、本件最高裁判決は、退職金に関する待遇差を中心に判断していますが、第1審及び第2審では、退職金以外の賃金手当に関する待遇差についても判断されています。
各賃金手当の待遇差に関する第1審、第2審及び第3審の判断を整理すると、以下のとおりです。
| 争点 | 第1審 | 第2審 | 第3審 |
|---|---|---|---|
| 比較対象社員 | 正社員一般(非限定) | 売店業務従事正社員に限定 | 売店業務従事正社員に限定 |
| 職務の内容 | 従事する業務の内容およびその業務に伴う責任の程度に大きな相違がある | 売店業務従事正社員は代務業務やエリアマネージャー業務に従事するなどの相違がある | 売店業務従事正社員は代務業務やエリアマネージャー業務に従事するなどの相違がある |
| 変更の範囲 | 職務の内容および配置の変更の範囲についても明らかな相違がある | 売店業務従事正社員は売店業務以外への配置転換の可能性がある等の相違がある | 売店業務従事正社員は売店業務以外への配置転換の可能性がある等の相違がある |
| 本給 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 資格手当 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 住宅手当 | ◯ | ✕ | ✕ |
| 残業手当割増率の差異 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 賞与 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 退職金 | ◯ | ✕ 正社員の4分の1 |
◯ |
| 褒賞金 | ◯ | ✕ | ✕ |
◯:不合理ではない
✕:不合理
第1審の判断内容
第1審である東京地判平成29年3月23日は、残業手当の割増率に関する待遇差以外は、いずれも不合理な待遇差にはあたらないと判断しました。
第1審の判断内容は、企業側の主張がほぼ認められている背景には、契約社員Bと比較対象とされる正社員の範囲が、「売店業務に従事する正社員のみならず、広く被告の正社員一般」と解されたことにあります。
第2審(本件高裁判決)の判断内容
一方、本件高裁判決は、第1審とは異なり、契約社員Bと比較対象とされる正社員の範囲について、以下のように限定的に解釈しました。
第1審原告らは、契約社員Bと比較対象すべき第1審被告の無期契約労働者を、正社員全体ではなく、売店業務に従事している正社員(互助会から転籍した者及び契約社員Aから登用された者。以下同じ。)に限定しているのであるから、当裁判所もこれに沿って両者の労働条件の相違が不合理と認められるか否かを判断することとする(なお、比較対象すべき第1審被告の無期契約労働者を正社員全体に設定した場合、契約社員Bは売店業務のみに従事しているため、それに限られない業務に従事している正社員とは職務の内容が大幅に異なることから、それだけで不合理性の判断が極めて困難になる。)。
このように、本件高裁判決は、契約社員Bと比較対象とされる正社員の範囲を、売店業務に従事している正社員に限定的に解釈したことによって、第1審と異なり、多くの賃金手当に関し、不合理な待遇差があると判断しました。
さらに、本件高裁判決は、正社員と契約社員との間における退職金の待遇差に関し、以下のように判示しました(下線部は筆者追記)。
① 一般に、退職金には賃金の後払い、功労報償等の様々な性格があるところ、長期雇用を前提とする無期労働契約を締結した労働者(以下「無期契約労働者」という。)に対し、福利厚生を手厚くし、有為な人材の確保及び定着を図るなどの目的をもって退職金制度を設ける一方、本来的に短期雇用を前提とした有期労働契約を締結した労働者(以下「有期契約労働者」という。)に対し、これを設けないという制度設計自体は、人事施策上一概に不合理であるとはいえない。
② もっとも、第1審被告においては、契約社員Bは契約期間が1年以内の有期契約労働者であり、賃金の後払いが予定されているとはいえないが、原則として契約が更新され、定年が65歳と定められており、実際に第1審原告らは定年により契約が終了するまで10年前後の長期間にわたって勤務したことや、契約社員Aは平成28年4月に職種限定社員として無期契約労働者となるとともに退職金制度が設けられたことを考慮すれば、少なくとも長年の勤務に対する功労報償の性格を有する部分に係る退職金、具体的には正社員と同一の基準に基づいて算定した額の4分の1に相当する額すら一切支給しないことは不合理である。
③ したがって、売店業務に従事している正社員と契約社員Bとの間の退職金に関する労働条件の相違は、労使間の交渉や経営判断の尊重を考慮に入れても、第1審原告らのような長期間勤務を継続した契約社員Bに全く退職金の支給を認めない点において、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たる。
以上のように、本件高裁判決は、少なくとも正社員の4分の1に相当する額すら支給しないことは、労働契約法20条に違反すると判断しました
本件最高裁判決の判断内容
これに対し、本件最高裁判決は、第2審とも異なり、正社員と契約社員Bとの間における退職金の待遇差に関し、以下のように判示しました。
労働契約法20条の判断基準
本件最高裁判決は、退職金に関する待遇差に関し、労働契約法20条違反の判断基準について以下のように判示しました。
労働契約法20条は、有期労働契約を締結した労働者と無期労働契約を締結した労働者の労働条件の格差が問題となっていたこと等を踏まえ、有期労働契約を締結した労働者の公正な処遇を図るため、その労働条件につき、期間の定めがあることにより不合理なものとすることを禁止したものであり、両者の間の労働条件の相違が退職金の支給に係るものであったとしても、それが同条にいう不合理と認められるものに当たる場合はあり得るものと考えられる。もっとも、その判断に当たっては、他の労働条件の相違と同様に、当該使用者における退職金の性質やこれを支給することとされた目的を踏まえて同条所定の諸事情を考慮することにより、当該労働条件の相違が不合理と評価することができるものであるか否かを検討すべきものである。
本件最高裁判決は、退職金の性質や支給することになった目的を考慮すると正面から提示しました。
なお、上記判断基準は、本件最高裁判決と同日に言い渡された 大阪医科大学事件最高裁判決と同様の判断基準となります。
本件におけるあてはめ
上記判断基準を示した上で、本件最高裁判決は、退職金に関する待遇差について、4つの判断要素に照らし、労働契約法20条には違反しないと結論づけました。
退職金の性質
第1審被告は、退職する正社員に対し、一時金として退職金を支給する制度を設けており、退職金規程により、その支給対象者の範囲や支給基準、方法等を定めていたものである。そして、上記退職金は、本給に勤続年数に応じた支給月数を乗じた金額を支給するものとされているところ、その支給対象となる正社員は、第1審被告の本社の各部署や事業本部が所管する事業所等に配置され、業務の必要により配置転換等を命ぜられることもあり、また、退職金の算定基礎となる本給は、年齢によって定められる部分と職務遂行能力に応じた資格及び号俸により定められる職能給の性質を有する部分から成るものとされていたものである。
このような第1審被告における退職金の支給要件や支給内容等に照らせば、上記退職金は、上記の職務遂行能力や責任の程度等を踏まえた労務の対価の後払いや継続的な勤務等に対する功労報償等の複合的な性質を有するものであり、第1審被告は、正社員としての職務を遂行し得る人材の確保やその定着を図るなどの目的から、様々な部署等で継続的に就労することが期待される正社員に対し退職金を支給することとしたものといえる。
本件最高裁判決は、正社員としての職務を遂行し得る人材の確保やその定着を図るなどの目的と認定しました。
なお、本件最高裁判決の認定理由は、 賞与に関する大阪医科大学事件最高裁判決とほぼ同様の言い回しとなっています。
職務の内容
そして、第1審原告らにより比較の対象とされた売店業務に従事する正社員と契約社員Bである第1審原告らの労働契約法20条所定の「業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度」(以下「職務の内容」という。)をみると、両者の業務の内容はおおむね共通するものの、正社員は、販売員が固定されている売店において休暇や欠勤で不在の販売員に代わって早番や遅番の業務を行う代務業務を担当して いたほか、複数の売店を統括し、売上向上のための指導、改善業務等の売店業務のサポートやトラブル処理、商品補充に関する業務等を行うエリアマネージャー業務に従事することがあったのに対し、契約社員Bは、売店業務に専従していたものであり、両者の職務の内容に一定の相違があったことは否定できない。
前記のとおり、本件最高裁判決は、契約社員Bと比較対象となる正社員を、「売店業務に従事する正社員」と限定してします。
その上で、契約社員Bと正社員の職務内容は、「一定の相違」と認定しています。なお、本件最高裁判決のいう「一定の相違」とは、大阪医科大学事件最高裁判決における「相当に軽易」という表現と比べると、それほど職務内容の違いは大きくないと解されたものとみることができます。
職務の内容及び配置の変更の範囲
また、売店業務に従事する正社員については、業務の必要により配置転換等を命ぜられる現実の可能性があり、正当な理由なく、これを拒否することはできなかったのに対し、契約社員Bは、業務の場所の変更を命ぜられることはあっても、業務の内容に変更はなく、配置転換等を命ぜられることはなかったものであり、両者の職務の内容及び配置の変更の範囲(以下「変更の範囲」という。)にも一定の相違があったことが否定できない。
本件最高裁判決は、変更の範囲には契約社員Bと正社員との間で相違があったことを認めています。
その他の事情
さらに、第1審被告においては、全ての正社員が同一の雇用管理の区分に属するものとして同じ就業規則等により同一の労働条件の適用を受けていたが、売店業務に従事する正社員と、第1審被告の本社の各部署や事業所等に配置され配置転換等を命ぜられることがあった他の多数の正社員とは、職務の内容及び変更の範囲につき相違があったものである。そして、平成27年1月当時に売店業務に従事する正社員は、同12年の関連会社等の再編成により第1審被告に雇用されることとなった互助会の出身者と契約社員Bから正社員に登用された者が約半数ずつほぼ全体を占め、売店業務に従事する従業員の2割に満たないものとなっていたものであり、上記再編成の経緯やその職務経験等に照らし、賃金水準を変更したり、他の部署に 配置転換等をしたりすることが困難な事情があったことがうかがわれる。このように、売店業務に従事する正社員が他の多数の正社員と職務の内容及び変更の範囲を異にしていたことについては、第1審被告の組織再編等に起因する事情が存在したものといえる。また、第1審被告は、契約社員A及び正社員へ段階的に職種を変更するための開かれた試験による登用制度を設け、相当数の契約社員Bや契約社員Aをそれぞれ契約社員Aや正社員に登用していたものである。これらの事情については、第1審原告らと売店業務に従事する正社員との労働条件の相違が不合理と認められるものであるか否かを判断するに当たり、労働契約法20条所定の「その他の事情」(以下、職務の内容及び変更の範囲と併せて「職務の内容等」という。)として考慮するのが相当である。
本件最高裁判決は、売店業務従事正社員と他の正社員との違いについては組織再編等に起因する事情を考慮要素としました。
また、職種変更するための登用制度があることも考慮要素として挙げています。大阪医科大学事件最高裁判決においても、職種変更するための試験制度があることが「その他の事情」と挙げられており、結果として不合理な待遇差には当たらない事情として評価されていることは、注意する必要があります。
結論
そうすると、第1審被告の正社員に対する退職金が有する複合的な性質やこれを支給する目的を踏まえて、売店業務に従事する正社員と契約社員Bの職務の内容等を考慮すれば、契約社員Bの有期労働契約が原則として更新するものとされ、定年が65歳と定められるなど、必ずしも短期雇用を前提としていたものとはいえず、第1審原告らがいずれも10年前後の勤続期間を有していることをしんしゃくしても、両者の間に退職金の支給の有無に係る労働条件の相違があることは、不合理であるとまで評価することができるものとはいえない。
なお、契約社員Aは平成28年4月に職種限定社員に改められ、その契約が無期労働契約に変更されて退職金制度が設けられたものの、このことがその前に退職した契約社員Bである第1審原告らと正社員との間の退職金に関する労働条件の相違が不合理であるとの評価を基礎付けるものとはいい難い。また、契約社員Bと職種限定社員との間には職務の内容及び変更の範囲に一定の相違があることや、契約社員Bから契約社員Aに職種を変更することができる前記の登用制度が存在したこと等からすれば、無期契約労働者である職種限定社員に退職金制度が設けられたから といって、上記の判断を左右するものでもない。
本件最高裁判決の結論部分をみると、以下のように判断していることがうかがわれます。
- 契約社員Bが短期雇用を前提としていないとしても、不合理とはいえない
- 契約社員Bと契約社員A(職種限定社員)との比較(ただし、限定的)
- 契約社員Bから契約社員Aへの職種変更の登用制度があることは不合理性を否定する事情になる
結論として、本件最高裁判決は、上記諸事情を踏まえ、退職金に関する待遇差は、不合理とはいえないと判断しています。
本件最高裁判決における反対意見
なお、本件最高裁判決には、宇賀克也裁判官の反対意見も述べられています。
反対意見では、「多数意見とは異なり、本件の事実関係の下で、長年の勤務に対する功労報償の性格を有する部分に係る退職金、具体的には正社員と同一の基準に基づいて算定した額の4分の1に相当する額すら契約社員Bに支給しないことが不合理であるとした原審の判断は是認することができ、第1審被告の上告及び第1審原告らの上告は、いずれも棄却すべきものと考える。」と述べられています。
かかる反対意見は、以下の理由から、本件最高裁判決と異なり、退職金に関する待遇差は違法であると述べています(以下は筆者の要約になります)。
- 退職金の、継続的な勤務等に対する功労報償という性質は、契約社員Bにもあてはまる。
- 売店業務に従事する正社員と契約社員Bの職務の内容や変更の範囲に大きな相違はない。
- 第1審被告の正社員に対する退職金の性質の一部は契約社員Bにも当てはまり、売店業務に従事する正社員と契約社員Bの職務の内容や変更の範囲に大きな相違はないことからすれば、両者の間に退職金の支給の有無に係る労働条件の相違があることは、不合理であると評価することができる。
このように、本件最高裁判決には反対意見もあることからすると、退職金に関する待遇差が不合理とはいえないとしても、その判断は必ずしも容易に断言できるものではないと考えられます。
本件最高裁判決の実務上の影響
本件最高裁判決は、本件高裁判決(控訴審判決)と異なり、正社員と有期契約社員の間の退職金に関する待遇差は、労働契約法20条に違反しないと判断しました。
もっとも、本件最高裁判決は、正社員と有期契約社員の間の退職金に関する待遇差等は、一律に違法ではないと断じたわけではありません。
本件最高裁判決自身が述べるように、「両者の間の労働条件の相違が退職金の支給に係るものであったとしても、それが同条にいう不合理と認められるものに当たる場合はあり得る」ものです。
本件最高裁判決は、あくまでも事例判決に過ぎず、退職金に関する待遇差がすべて合法であると判断されたわけではありません。
また、本件最高裁判決には反対意見も付されているように、本件事実関係に照らし、必ずしも不合理かどうかの判断は容易ではないと評価することもできます。
本件最高裁判決後も、正社員と有期契約社員の間の退職金に関する待遇差が違法と解されるケースはあり得ますので、企業としては、退職金の有無や支給額等、人事評価制度を検討する必要があることには変わりありません。
今後も退職金の支給の有無等に関する正社員と有期契約社員の待遇差に関しては、個別の裁判例の集積をみながら、合理性に関する判断基準を見極める必要があります。
出典・引用
[1] 裁判所HP|令和元年(受)第1190号,第1191号 損害賠償等請求事件 令和2年10月13日 第三小法廷判決(PDF)