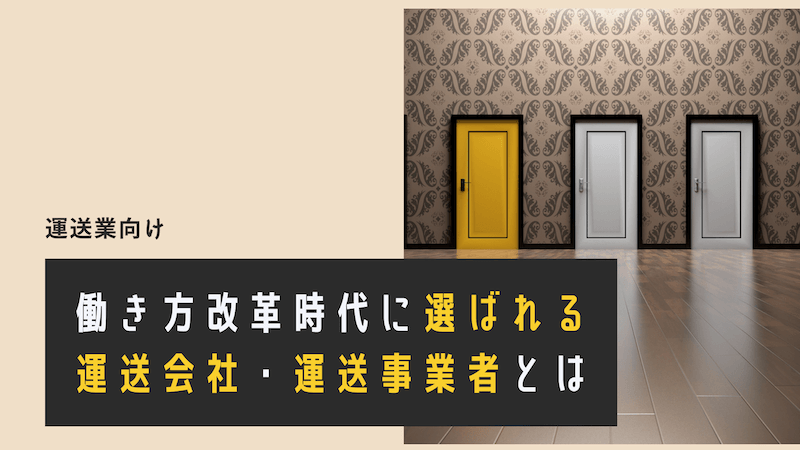はじめに
2024年問題への対応が急がれる中、多くの運送事業者様が見落としがち、あるいは対応が後回しになっている重要な法改正があります。それが、2023年4月1日から中小企業にも全面的に適用が開始された、「月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率の引き上げ」です。
具体的には、1か月の時間外労働が60時間を超えた部分については、割増率を従来の25%以上から「50%以上」で計算しなければなりません。これまで長時間労働が常態化しがちであった運送業界にとって、この改正は人件費に直接的なインパクトを与える、非常に重大な変更です。
時間外労働の上限規制(年960時間)や改善基準告示の遵守とあわせて、この割増賃金率のルールに正しく対応しなければ、未払い残業代のリスクが雪だるま式に膨れ上がる危険性があります。
本記事では、この月60時間超の割増賃金率引き上げについて、具体的な計算方法、人件費負担を緩和する「代替休暇」制度の活用法、そして給与計算システムや就業規則で今すぐ見直すべき法的ポイントを、弁護士が分かりやすく解説します。
Q&A
Q1. 「月60時間」の時間外労働をカウントする際に、休日労働の時間も含まれますか?
いいえ、含まれません。この「月60時間」は、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた「時間外労働」のみをカウントします。法定休日に労働させた場合の「休日労働」の時間は、割増率50%の計算の基礎となる月60時間の算定からは除外されます。ただし、休日労働には別途35%以上の割増賃金の支払い義務がありますので、混同しないよう注意が必要です。
Q2. 人件費の負担を軽減できる「代替休暇」制度とは、具体的にどのような制度ですか?
代替休暇とは、月60時間超の時間外労働を行った労働者に対して、引き上げられた割増賃金(50%-25%=25%部分)の支払いに代えて、有給の休暇を与えることができる制度です。人件費の支払いを抑制しつつ、ドライバーの休息を促進できるメリットがありますが、導入には厳格な要件である「労使協定の締結」が不可欠です。
Q3. 当社では固定残業代(みなし残業代)制度を導入していますが、今回の法改正で何か影響はありますか?
非常に大きな影響があります。まず、貴社の固定残業代が、月60時間超の50%割増分まで含んだ設計になっているかを確認する必要があります。もし、従来の25%の割増率でしか計算されていない場合、月60時間を超えて残業した従業員に対しては、差額となる25%分の割増賃金を追加で支払わなければなりません。この点を曖昧にしたまま放置すると、固定残業代制度そのものが無効と判断され、過去に遡って莫大な未払い残業代の支払いを命じられるリスクがあります。
解説
法改正の概要 – 労働基準法第37条の改正とその影響
労働基準法第37条は、時間外労働、休日労働、深夜労働に対する割増賃金について定めています。これまで、月60時間超の時間外労働に対する50%以上の割増賃金率は大企業のみに適用され、中小企業には猶予措置が取られていました。しかし、その猶予措置が2023年3月31日をもって廃止され、同年4月1日から、すべての企業でこのルールが適用されることになりました。
【具体的な計算例】
例えば、1時間あたりの基礎賃金が2,000円のドライバーが、月に80時間の時間外労働を行った場合の割増賃金は以下のようになります。
改正前の計算
- 80時間 × 2,000円 × 1.25 = 200,000円
改正後の計算
- 60時間までの部分: 60時間 × 2,000円 × 1.25 = 150,000円
- 60時間を超える部分: 20時間 × 2,000円 × 1.50 = 60,000円
- 合計: 150,000円 + 60,000円 = 210,000円
このケースでは、1人あたり月10,000円の人件費増となります。これが全ドライバーに及ぶと、会社全体のコストに与える影響は小さくありません。
さらに、深夜時間帯(22時~翌5時)に月60時間超の時間外労働が重なった場合、割増率は「深夜割増25%+時間外割増50%=75%」となります。人件費のインパクトはさらに大きくなるため、正確な計算が不可欠です。
人件費増を抑制する「代替休暇」制度の活用法
この人件費負担の増加に対する一つの選択肢が、「代替休暇」制度の導入です。これは、引き上げ分の割増賃金の支払いを、有給休暇に振り替えることができる制度です。
導入の要件
代替休暇制度を導入するには、必ず「労使協定」を締結する必要があります。会社の判断だけで一方的に導入することはできません。
労使協定で定めるべき事項
代替休暇の時間数の具体的な算定方法
月60時間超の時間外労働時間数に、換算率(※)を乗じて計算します。(※換算率 = (1.5 – 1.25) ÷ 1.5 ≒ 0.167ではありません。法律で計算式が定められています。)
正しい計算式
(月の時間外労働時間数 – 60)× 換算率(※)(※換算率 = 引き上げ後の割増率 50% – 引き上げ前の割増率 25%)=0.25
- 代替休暇の単位
1日または半日単位で与えることが基本です。 - 休暇を与えることができる期間
月60時間超の残業が発生した月の末日の翌日から、2か月以内とされています。 - 休暇を取得するかどうかの労働者の意思確認の方法など。
メリットとデメリット
- メリット
割増賃金の支払いを抑制できる。ドライバーの休息を促進し、健康確保や安全運行に繋がる。 - デメリット
労使協定の締結や休暇管理の手間が増える。ドライバーが休暇取得を希望せず、結局、割増賃金を支払うケースも想定される。
導入にあたっては、これらのメリット・デメリットを比較衡量し、自社の実態に合った制度設計を行うことが重要です。
給与計算・就業規則で対応すべきこと
この法改正に対応するため、企業は以下の2つの側面から見直しを行う必要があります。
① 給与計算の実務対応
- 勤怠管理の徹底
まず前提として、毎月の時間外労働時間を正確に把握する必要があります。特に「1か月の起算日」をいつにするか(例:毎月1日、賃金締切日の翌日など)を明確にしなければなりません。 - 給与計算システムの確認・改修
現在使用している給与計算システムが、月60時間超の割増率50%の計算に自動で対応しているかを確認します。対応していない場合は、システムのアップデートや改修、あるいは手計算での正確な処理が必要です。計算ミスは、そのまま未払い賃金に繋がります。
② 就業規則(賃金規程)の変更
- 割増賃金率の明記
就業規則の一部である賃金規程に、「1か月の時間外労働が60時間を超えた部分については、50%以上の率で計算した割増賃金を支払う」旨を明確に規定する必要があります。 - 代替休暇制度の規定
代替休暇制度を導入する場合には、労使協定で定めた内容(算定方法、取得手続きなど)を就業規則にも記載します。 - 固定残業代制度の見直し
固定残業代(みなし残業代)を導入している企業は、特に注意が必要です。- 有効性の確認
そもそも、その固定残業代制度が法的に有効か(①明確区分性、②対価性、③差額支払いの合意が満たされているか)を再確認します。 - 割増率の確認
雇用契約書や賃金規程で、固定残業代に「月60時間超の50%割増分を含む」と明記されているかを確認します。明記されていない場合、差額の支払い義務が生じます。この機会に、固定残業代が何時間分の時間外労働に対するものなのか、その金額の内訳(通常割増分、60時間超割増分)を明確に規定し直すことが、将来のトラブルを防ぐ上で賢明です。
- 有効性の確認
弁護士に相談するメリット
割増賃金に関する問題は、運送業における労務トラブルの最大の火種です。専門家である弁護士に相談することで、リスクを未然に防ぐことができます。
- 法的に有効な賃金制度の設計
貴社の実態に合わせて、固定残業代制度や歩合給制度が、今回の法改正を含めた最新の法令や判例に照らして有効かどうかを診断し、リスクの少ない賃金制度への見直しをサポートします。 - 代替休暇導入のサポート
代替休暇制度を導入する際の、法的に不備のない労使協定書の作成から、就業規則への規定方法、従業員への説明まで支援します。 - 就業規則(賃金規程)の全面的な見直し
今回の改正点だけでなく、2024年問題全体に対応した、会社を将来のリスクから守るための就業規則・賃金規程の作成・改定を全面的に行います。 - 労働基準監督署の調査対応
万が一、未払い残業代等で労働基準監督署の調査が入った場合にも、適切な対応を助言します。
まとめ
月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の引き上げは、すべての運送事業者に関わる、避けて通れない法改正です。この対応を怠れば、人件費コストの増大に苦しむだけでなく、高額な未払い残業代請求という形で、経営に深刻なダメージを受ける可能性があります。
まずは、自社の給与計算が正しく行われているか、就業規則や固定残業代の定めが法的に問題ないかを、今すぐ点検してください。そして、必要に応じて代替休暇制度の導入を検討するなど、プロアクティブな対応が求められます。
賃金制度は、企業の根幹をなす非常にデリケートな問題です。少しでも不安や疑問があれば、自己判断で進めず、弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。法務の専門家が、貴社の健全な経営をサポートいたします。
長瀬総合の運送業専門サイト
2024年4月1日からの働き方改革関連法施行により、物流業界での働き方が今までと大きく異なっていきます。
違反してしまうと刑事罰の対象になってしまうので、運送・物流業を営む方の対策は必須です。
「どうしたら良いかわからない」という方は当事務所までご相談ください。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス