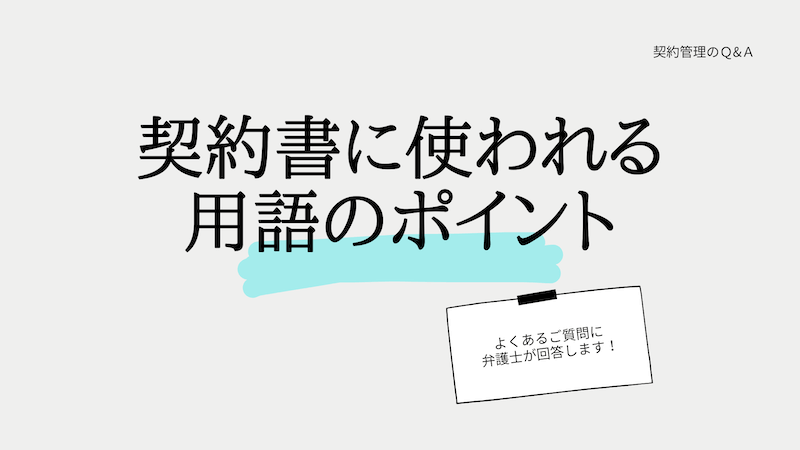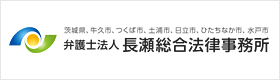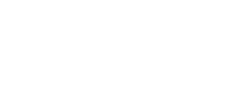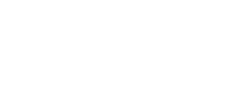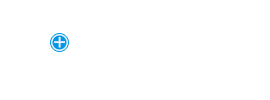はじめに
賃貸建物の明渡請求でいわゆる催告解除の方法をとる場合に関する問題点について解説したいと思います。
催告解除の通知の内容
催告兼解除通知の一般的な内容
通知書の内容は、大きく分けて2つの内容で構成されます。
1点目は、賃料が未払い状態にあること、賃料等の総額などを示し、賃料の振込先を載せて賃料の支払いを催促することです。
2点目は、通知が届いてから「相当の期間」が経過するまでに支払いがない場合には、賃貸借契約を解除するという意思表示です。後述するように、相手方に通知が届いた日が相当期間の起算点となりますので、到達のタイミングが確認できるように、内容証明郵便を利用して通知を送るべきでしょう。
「相当の期間」の意味
相当の期間とは、賃借人が返済を行うために必要な期間を意味します。
支払い催告と賃貸借契約解除の意思表示との間に相当の期間があったと言えるかが問題となった判例[1]では、相当の期間について「もとより、民法541条のいう相当の期間がどれくらいかは、各場合について債務の内容と取引慣行とを考慮し債権法を支配する信義誠実の原則に従って決するよりほかはないが、同条がすでに履行期を徒過している債務者に対しても最後の履行の機会を与えもって解除を免れる余地を残すというにあるのであるから、同条にいう相当の期間とは、催告をうけて初めて履行の準備にかかりこれを完了するに要する期間ではなくて、すでに履行の準備が大体できているものを提供するに要する時間と解するのが相当である。」と摘示されています。
また、相当の期間が具体的にどのくらいの期間を示すのかという点ですが、上記最高裁では「5月1日催告したのち5日になした解除の意思表示は、たとえ5月2日が土曜日、3日、5日が休日であったとしても、なお相当の期間を経過したのちなされたものであり有効である」と判断しています。相当期間を5日間とした場合の解除も有効であるとされていますので、催告解除をする場合には、5日ないし7日間の期間を設けて催告すべきであるといえます。
相当期間の明示は必要か
通知に、「本通知到着後5日(ないし7日)以内に」といった相当期間の明示が必要なのでしょうか。
これについて判例[2]は、「必ス常ニ始メヨリ一定ノ日時若ハ期間ヲ明示スルヲ要ストノ意ニアラス催告ノ時ト解除ノ時トノ間ニ既ニ相当ノ時ヲ経過シ居レハ是亦足レリ」と指摘し、明示は不要という立場をとっています。
法定更新の場合の更新手数料の請求
催告兼解除通知書には、未払賃料総額を明示して請求しますが、賃貸借契約が法定更新されている場合、更新手数料や事務手数料は請求できるのでしょうか。
賃貸借契約では、契約期間が設けられ、契約を継続する場合には更新可能とする規定が盛り込まれているのが一般的です。また、更新については協議の上更新をすることができるといった合意更新を前提にしているものが一定数あります。さらに、更新手続の費用として更新手数料を設定している場合もあります。
賃貸借契約が法定更新されている場合、更新手数料を請求することができるのか問題となりますが、裁判例[3]では合意更新された場合の規定であると解釈するのが文言上自然であり、法定更新された場合には更新手数料につき賃借人に支払義務はないとされました。
したがって、賃料の未払期間に法定更新のタイミングが含まれる場合、更新手数料は請求することができないため、催告兼解除通知で請求する金額には、更新手数料を加えないという点に注意が必要です。
解除通知の送付方法
一般的な送付方法
通知は内容証明郵便で送るべきでしょう。相手方へ配達されれば配達証明が送られてくるため、いつ賃借人に通知が配達されたのか容易に明らかにすることが可能となります。
もっとも、内容証明郵便を相手が受け取らず、再配達依頼もしない場合には、保管期間経過により通知が返送されてしまう場合もあります。
このような場合、通知が届かないために解除ができないということになってしまうのでしょうか(これが認められるとすれば、賃借人は通知を受領をしないことで居座り続けることが可能になってしまうため、不合理な結論になってしまいます)。
「到達」したといえるための要件
どうすれば通知が到達したといえるのかという点、最高裁[4]は「「到達」とは意思表示(通知)の受領者がその意思表示(通知)を受領し得る状態におかれることであり、相手方においてその意思表示を認識したるや否や、その了知したるや否やはこれを問はず、その効力を発生せしめる」「相手方をして意思表示の内容を了知せしむべく表意者の側として常識上為すべきことを為し了りたる時を以て意思表示は相手方に到達したるものとし其以後の推移と運命は一に之を相手方の危険に移すものこれが所謂到達主義の要諦であると云わねばならない」としました。
また、別の判例[5]でも、上記判断が引用されており、「到達とは…相手方の了知可能な状態に置かれることをもって足りるものと解される」とされています。
以上から、到達したか否かについては、①郵便物の受領可能性、②内容の推知可能性、の2点から判断されると整理することができます。
①との関係では、「郵便物が郵便受箱に入れられたり、同居人がこれを受領するなど、意思表示を記載した書面が相手方のいわゆる勢力範囲(支配圏)内におかれることをもって足りると解されている」という指摘がされています[6]。
また、②との関係では、「飽くまで当該具体的事案における個別的判断によることに注意を要する。例えば、かねて特定の債権者から支払いが督促されていたような場合には、不在配達通知書に差出人としてこの債権者の氏名が記載されていれば、受取人において、郵便物が督促状(支払の催告)であると推知しうるであろうし、ある日突然に全く面識のない弁護士から内容証明郵便が送付されてきたような場合は、直ちにその内容を推知することは容易ではないだろう」と指摘されています[7]。
上記を踏まえた送付の工夫
内容証明郵便で通知を送る方法は行うべきでしょう。それに合わせて、特定記録などを活用し、内容証明郵便と同時に通知を送るという方法が考えられます。特定記録は受け付けた日時を記録しますが、通知自体はポスト投函になるため、賃借人が不在等の場合でも賃借人の手元に届けることが可能です。
また、レターパックなどを用いて通知を送る方法もありますが、その際に送り主に賃貸人等の関係者氏名を入れることで、賃借人が内容を推知することが可能になる場合もあります。
いずれにしても、それまでの交渉経緯を踏まえて、どのような送付方法をとるべきかは、事案ごとに検討する必要があります。
おわりに
以上、催告をして賃貸借契約を解除する場合の方法や留意点について見てまいりました。次回は、解除通知を送った後の訴訟提起と執行の申立について解説します。
[1] 最判昭和39年10月27日
[2] 大審院昭和2年2月2日判決
[3] 東京地判平成23年4月27日
[4] 最判昭和36年4月20日
[5] 最判平成10年6月11日
[6] 脚注5判例解説(判例タイムズ979号87頁、金融法務事情1525号54頁)
[7] 前掲6