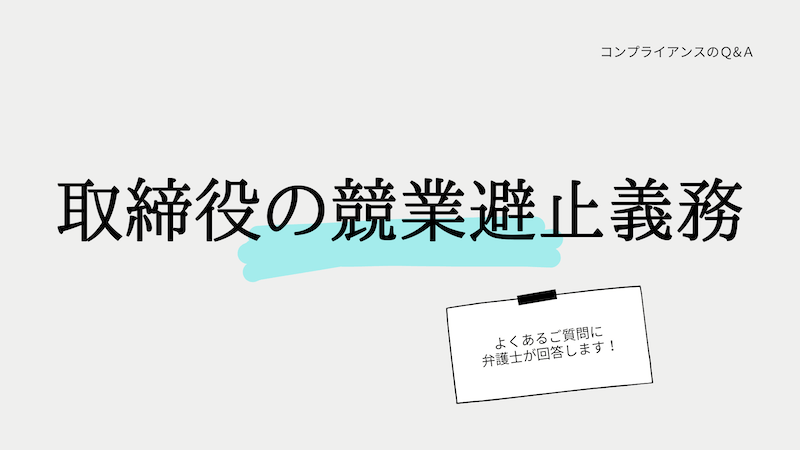親子会社・兄弟会社間での取引
質問
当社(甲社)には、100%親会社として乙社がいますが、乙社の取締役は当社の代表取締役を兼務しています。この場合、当社と乙社との間での取引は競業取引に該当するのでしょうか。
また、当社には、乙社を親会社とする兄弟会社である丙社もいますが、当社と丙社との取引も競業取引に該当するのでしょうか。
回答
乙社が甲社の100%親会社であれば、甲乙間での取引は完全親子会社間での取引であり、利害が対立する関係にはないことから、会社法356条1項が規制する競業取引には該当しないものと思われます。
また、兄弟会社である甲・丙社間での取引も、乙社が丙社にとっても100%親会社であれば、甲・丙間での取引と乙社の利害が対立する関係にはないことから、競業取引には該当しないものと思われます。
解説
取締役の競業避止義務
取締役は、会社の業務執行又はその決定に関与するため、会社のノウハウや顧客その他の会社の内部情報を知り、又は入手しやすい立場にあるため、このような地位にある取締役が会社と競合する取引に従事すると、本来会社の事業のために用いられるべき情報や取引関係が、取締役の行う競争事業のために利用されるおそれが大きいと言えます。
そこで、会社法は、取締役が会社の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図るおそれの大きい行為をしようとするときは、当該取締役は株主総会(又は取締役会)において当該取引に関する重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない、とされています。(会社法356条1項、365条。いわゆる競業避止義務)
親子会社間の競業取引
かかる趣旨に鑑みると、親会社と子会社が同種の事業を行う場合に、親会社の取締役が子会社の代表取締役を兼任し、子会社を代表して親会社の「事業の部類に属する取引」を行う場合も、子会社に、当該親会社以外の株主が存するときは、親会社の利益と子会社の利益が衝突する可能性がある以上、本条の適用があるものとされています。
これに対して、完全親子会社間の場合は、親子会社間に利害の対立がないことから、競業避止義務の趣旨が妥当せず、同条の適用はないものと解されています(大阪地裁昭和58年5月11日金判678号)。
ただし、完全親子会社の場合であっても、子会社が倒産すれば、子会社の財産は子会社の債権者の担保財産となり、株主である親会社に優先することから、親子会社間に利害の対立がないとはいえないとして、本条の適用を認める見解もあることに注意が必要です。
兄弟会社間の競業取引
これに対して、兄弟会社間の取引と会社法356条の適用の有無については、直接言及した文献は見当たりません。
もっとも、会社法356条の趣旨に鑑みると、兄弟会社双方にとっての株主が100%親会社のみであれば、兄弟会社間での取引の結果、双方の株主(=100%親会社)の利益が害されることにはならないことから、完全親子会社間の取引と同様、利益相反関係がないものとして本条の適用がないものと整理することも合理的と思われます。
ご相談のケースについて
乙社が甲社の100%親会社であれば、甲乙間での取引は完全親子会社間での取引であり、利害が対立する関係にはないことから、会社法356条1項が規制する競業取引には該当しないものと思われます。
また、兄弟会社である甲・丙社間での取引も、乙社が丙社にとっても100%親会社であれば、甲・丙間での取引と乙社の利害が対立する関係にはないことから、競業取引には該当しないものと思われます。
取締役兼株主による競業取引
質問
当社(甲社)の取締役Xは、当社の一人株主でもあります。かかるXが、当社と取引をする場合、会社法で規制されている競業取引に該当するでしょうか。
また、当社のグループ会社乙社の取締役Yは、乙社の100%株主ではありませんが、ライバル会社丙社の株式30%を保有しており、しかも丙社の経営を実質的に支配している場合に、Yが丙社と取引することは競業取引に該当するでしょうか。
回答
取締役Xが甲社の100%株主である場合には、Xと甲社との間に利害が対立する関係にないため、競業取引には該当しないものと思われます。
これに対して、グループ会社乙社の取締役Yが競合会社丙社の30%の株式を保有し、かつ、丙社の経営を実質的に支配している場合には、乙社と丙社との利害が対立する事態が想定されることから、競業取引に該当するものと思われます。
解説
取締役の競業避止義務
取締役は、会社の業務執行又はその決定に関与するため、会社のノウハウや顧客その他の会社の内部情報を知り、又は入手しやすい立場にあるため、このような地位にある取締役が会社と競合する取引に従事すると、本来会社の事業のために用いられるべき情報や取引関係が、取締役の行う競争事業のために利用されるおそれが大きいと言えます。
そこで、会社法は、取締役が会社の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図るおそれの大きい行為をしようとするときは、当該取締役は株主総会(又は取締役会)において当該取引に関する重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない、とされています。(会社法356条1項、365条。いわゆる競業避止義務)
取締役兼一人株主による競業取引
前述のとおり、会社法が取締役に対して競業避止義務を課した趣旨は、取締役と会社(=株主)の利害が対立し、会社(=株主)の利益が害される事態を防止することにあるものといえます。
かかる趣旨からすると、会社の全株式を保有する取締役と会社との間では、取締役と株主とが同一人物であり、取締役と株主の利害が対立する事態が生じ得ないことから、競業避止義務を課す必要はないものと思われます。
なお、競業取引については、株主全員の同意がある場合には取締役会の承認は不要と考えられていることからも、競業取引を行う取締役が会社の全株式を保有する場合は、一人株主の同意がある場合と同視して、競業避止義務の対象とならないものと整理することも可能と思われます。
競業会社の株主を兼務する場合
これに対して、取締役が競業会社の役員は兼務していないものの株主である場合には、株主を兼務していることをもって直ちに競業取引に該当するものではないとしても、状況によっては会社と取締役との利害が対立する事態が想定され、競業取引に該当する可能性があるものと思われます。
具体的には、取締役が競業会社の経営を実質的に支配している場合には、当該取締役と会社との間の利害が対立するものといえ、取締役会の承認を要する競業取引に該当するものと思われます。
裁判例においても、競業会社の過半数の株式を保有していないものの、対抗しうる株式を保有する株主が存在しないことや、過去からの支配の経緯等から、事実上の主宰者として経営を支配してきたと認定した取締役について、旧商法264条(現会社法356条)の適用を認めたもの(大阪高裁平成2年7月18日判時1378号)があります。
また、家族により出資・運営されている競合会社について、出資持分は全く保有していないものの、運営資金を貸し付けていること、事業上不可欠な土地の賃借契約の連帯保証人となっていること等から、資金調達、信用及び営業について中心的役割を果たしているとして、事実上の主宰者と認定して競業避止義務違反を認定した裁判例があります。(名古屋高裁平成20年4月17日金判1325号)
ご相談のケースについて
取締役Xが甲社の100%株主である場合には、Xと甲社との間に利害が対立する関係にないため、競業取引には該当しないものと思われます。
これに対して、グループ会社乙社の取締役Yが競合会社丙社の30%の株式を保有し、かつ、丙社の経営を実質的に支配している場合には、乙社と丙社との利害が対立する事態が想定されることから、競業取引に該当するものと思われます。
取締役の親族による競業取引
質問
当社は広告代理店を営んでいますが、当社の取締役Xの妻Yは、当社に無断で、当社の事業と競合する広告ビジネスをライバル会社との間で始めようとしているようです。
当社の取締役の配偶者が会社と競合する取引を行う場合、会社法上の競業取引として取締役会の承認が必要ではないでしょうか。
回答
必ずしも明確な文献や判例等があるものではありませんが、ご相談のケースにおいて、取締役Xの妻Yが会社と競合する取引をしたとしても、単に取締役の親族が行うというだけでは取締役会の承認が必要となる競業取引には該当しないものと思われます。
解説
取締役の競業避止義務
取締役は、会社の業務執行又はその決定に関与するため、会社のノウハウや顧客その他の会社の内部情報を知り、又は入手しやすい立場にあるため、このような地位にある取締役が会社と競合する取引に従事すると、本来会社の事業のために用いられるべき情報や取引関係が、取締役の行う競争事業のために利用されるおそれが大きいと言えます。
そこで、会社法は、取締役が会社の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図るおそれの大きい行為をしようとするときは、当該取締役は株主総会(又は取締役会)において当該取引に関する重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない、とされています。(会社法356条1項、365条。いわゆる競業避止義務)
取締役の親族による競業取引
競業取引については、取締役が主宰者として経営する会社の取引については競業避止義務規制を及ぼすべきとの議論がなされている一方、取締役の親族が会社と競合する取引を行う場合に、会社法上の競業取引規制を及ぼすべきかについては、これまでほとんど議論されていません。
もっとも、競業取引は会社の業務と直接の関係のないところで行われるものであり、しかも取締役の親族が行う取引については、当該取締役自身も関知していないこともあり得ることから、競業取引の適用範囲を拡大することには慎重になるべきと思われます。
したがって、取締役が取引相手の会社の事実上の主宰者に該当するかの判断において、親族関係は一要素として考慮されることはあり得ると思われますが、単に取締役の配偶者であることをもって競業取引に該当するものと評価されることはないものと思われます。
これに対して、会社と取締役の親族との取引が利益相反取引に該当するか、については、いまだ判例の立場は明確ではなく、見解の対立があるものの、裁判例上、配偶者が社会的経済的に同一の生活実態を有していることなどを根拠に、利益相反取引に該当するものと判断したもの(仙台高裁平成9年7月25日)や、取締役の妻の債務を会社が保証することは取締役会の承認が必要な利益相反取引に該当すると判断したもの(東京高裁昭和48年4月26日)があり、実務上は取締役の親族と会社との取引も利益相反取引に該当する可能性があるものとして保守的な対応をとるケースが多いものと思われます。
参照
ご相談のケースについて
必ずしも明確な文献や判例等があるものではありませんが、ご相談のケースにおいて、取締役Xの妻Yが会社と競合する取引をしたとしても、単に取締役の親族が行うというだけでは取締役会の承認が必要となる競業取引には該当しないものと思われます。
退任取締役の競業避止義務
質問
私は現在IT企業A社の取締役を勤めていますが、このたび新たなビジネスチャンスを独自につかんだことから、A社の取締役を退任し、自分で会社を興してビジネスをはじめようと考えています。
取引先等、新たなビジネスはA社と競合する領域があり、また、A社の見所のある社員も何名か引き抜こうと考えているのですが、会社法上、何か問題があるでしょうか。
回答
取締役退任後であれば、会社と競業するビジネスであっても、原則として自由に行うことができます。
ただし、退任予定段階において、不当な態様で従業員を引き抜いた場合には、取締役の忠実義務に違反し、会社に対して損害賠償責任を負う可能性があります。
解説
取締役の競業避止義務
取締役の競業は、会社のノウハウや顧客情報等を奪う形で会社の利益を害するおそれが高いことから、取締役が自己又は第三者のために「会社の事業の部類に属する取引」をしようとするときは、その取引について重要な事実を開示して株主総会の承認(取締役会設置会社以外の場合。会社法356条1項1号。普通決議)/取締役会の承認(取締役会設置会社の場合。会社法365条1項)を受ける必要があります。
また、取締役会設置会社においては、競業取引をした取締役は、取引後遅滞なく当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければなりません(会社法365条2項・976条23号)。
「会社の事業の部類に属する取引」とは、会社が実際に行っている取引と目的物(商品・役務の種類)及び市場(地域・流通段階等)が競合する取引をいい、会社が進出を企図し、市場調査等を進めていた地域における同一商品の販売は規制対象になります(東京地裁昭和56年3月26日判時1015号)。また、「取引」には、販売・購入の双方を含み、たとえばある物品の製造・販売を目的とする会社であれば、その原材料を購入する取引も競業となり得ます(最高裁昭和24年6月4日)。
違反の効果
取締役が、株主総会・取締役会の競業の承認を得ないで取引をしたときは、当該取引によって同人又は第三者が得た利益の額を損害額として推定し、会社は同人に対して損害賠償を請求できます(会社法423条1項・2項)。また、総株主の同意がない限り、事後承認は認められません(会社法424条)。
ただし、株主総会・取締役会の承認を得たとしても、取締役の会社に対する責任が完全に免除された訳ではなく、当該競業により会社に損害が生じれば、当該競業行為に関し任務懈怠のある取締役は責任を免れないと解されていることに注意が必要です。
取締役退任後の競業
競業取引規制の対象となる「取締役」は、業務執行に関与する代表取締役又は代表取締役以外の業務執行取締役のみならず、すべての取締役が含まれますが、取締役退任後の競業は原則として自由に行うことができます。
また、取締役退任後の競業を禁止する取締役・会社間の特約は、取締役の職業選択の自由(憲法22条1項)に関わるため、①取締役の社内での地位、②営業秘密・得意先維持等の必要性、③地域・期間など制限内容、④代償措置等の諸要素を考慮し、必要・相当性が認められる限りにおいて公序良俗に反せず有効と解されています(東京地裁平成5年10月4日金判929号、東京地裁平成7年10月16日判時1556号等)。
退任予定の取締役による従業員の引き抜き
これに対して、退任後に会社と同一又は類似の事業を開始することを企図する取締役が、在任中に部下に対して退職して自己の事業に参加するよう勧誘することが、取締役の忠実義務違反となることがあることに注意が必要です(東京高裁平成元年10月26日金判835号、前橋地裁平成7年3月14日判時1532号)。
もっとも、部下への退職勧誘全てが忠実義務違反となるわけではなく、①取締役の退任の事情、②退職従業員と取締役の関係(自ら教育した部下か否か)、③人数等会社に与える影響の度合い等を総合誌、不当な態様のもののみが忠実義務違反となる、と解されています。
ご相談のケースについて
取締役退任後であれば、会社と競業するビジネスであっても、原則として自由に行うことができます。
ただし、退任予定段階において、不当な態様で従業員を引き抜いた場合には、取締役の忠実義務に違反し、会社に対して損害賠償責任を負う可能性があります。
参考文献
江頭憲治郎「株式会社法第6版」(株式会社有斐閣)
(注)本記事の内容は、記事掲載日時点の情報に基づき作成しておりますが、最新の法例、判例等との一致を保証するものではございません。また、個別の案件につきましては専門家にご相談ください。