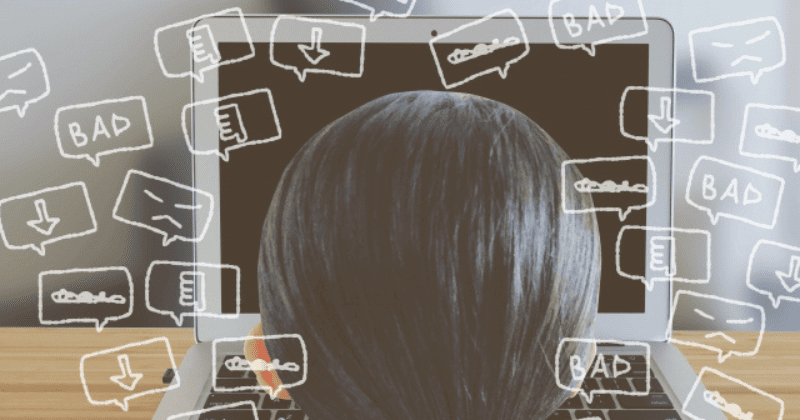はじめに
「サイトのフォームから何度も削除依頼を送っているのに、全く返事がない」
「運営者から『表現の自由の範囲内なので対応できない』と、けんもほろろに断られた」
ご自身で勇気を出して削除依頼のアクションを起こしたにもかかわらず、このような対応を取られ、途方に暮れてしまっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、ここで諦める必要はありません。
単なる「お願い」としての削除依頼が通じないときに、私たちが頼ることができるのが「情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)」という法律です。そして、この法律に基づいて行う正式な削除請求のことを「送信防止措置請求(そうしんぼうしそちせいきゅう)」と呼びます。
この記事では、単なる削除依頼と何が違うのか、どのような手続きなのか、そして、この請求を行うことで何が期待できるのか、「送信防止措置請求」のポイントを分かりやすく解説します。
Q&A
Q1. 「送信防止措置請求」と、以前自分で行った「削除依頼」とは、一体何が違うのですか?
最大の違いは、「法的根拠の有無」です。ご自身で行う削除依頼が、サイト運営者の任意の協力を求める「お願い」であるのに対し、「送信防止措置請求」は情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)という法律に定められた、被害者の正当な権利に基づく法的な請求です。この請求を受けたサイト運営者(法律上の「プロバイダ」)は、法律で定められたルールに則って対応する必要があり、単なるお願いと比べて、格段に重みのある請求となります。
Q2. 送信防止措置請求を行えば、書き込みは確実に削除されるのでしょうか?
残念ながら、確実ではありません。請求を受けたサイト運営者は、多くの場合、投稿者に対して「削除依頼が来ていますが、反論はありますか?」と意見を聞きます(意見照会)。もし投稿者が「権利侵害ではない」と反論した場合、サイト運営者は中立の立場を守るため、投稿を削除しないという判断を下すことが少なくありません。送信防止措置請求は、あくまでサイト運営者の任意での削除を促すための強力な手段であり、削除を法的に強制する力まではない、という限界があります。
Q3. 送信防止措置請求の請求書には、どのようなことを書けばよいのでしょうか?
請求書には、単に「消してほしい」と書くだけでは不十分です。法律の要件を満たすために、①請求者の氏名・住所、②問題の投稿が掲載されている場所(URL)、③掲載されている情報、④侵害されたとする権利、⑤権利が侵害されたとする理由、を明確に記載する必要があります。特に「⑤権利が侵害されたとする理由」の部分で、どの権利(名誉権、プライバシー権など)が、なぜ侵害されているのかを、法的観点から説得的に主張することが成功の鍵となります。
解説
1. 法律上の武器「送信防止措置請求」とは?
送信防止措置請求は、「情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)」という、ネット上の権利侵害に関する重要な法律に定められた手続きです。
目的
プロバイダ等(サイト運営者、SNS事業者、サーバー会社など)に対し、権利を侵害する情報の送信(=ネット上での公開)を防止する措置を講じるよう、法的な根拠をもって請求すること。
簡単に言えば、「法律に基づいて、この違法な書き込みを削除してください」と正式に要求する手続きです。
2. なぜプロバイダは請求に応じるのか?(免責の仕組み)
サイト運営者などのプロバイダは、常に「被害者の権利保護」と「投稿者の表現の自由」との間で、板挟みになるという難しい立場にあります。
- 権利侵害の投稿を放置すれば、被害者から「放置した責任がある」と訴えられるリスク。
- 正当な批判や意見まで削除すれば、投稿者から「表現の自由を不当に奪った」と訴えられるリスク。
このジレンマからプロバイダを救い、適切な対応を促すために、情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)は「免責要件」を定めています。つまり、「こういう条件を満たして削除したのであれば、プロバイダは投稿者から訴えられても責任を負わなくてよい」というお守りを与えるのです。
その主な免責要件が、以下の2つです。
他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があった場合
誰が見ても明らかに権利侵害であると判断できる場合。例えば、本人の同意なく、個人の電話番号や住所、裸の写真などが掲載されているケースです。このような場合は、プロバイダは投稿者の意見を聞かずに削除しても免責されます。
発信者(投稿者)に意見照会を行い、照会の到達日から7日を経過しても、発信者から送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申し出がなかった場合
権利侵害かどうかの判断が難しい場合、プロバイダは投稿者に対し、「あなたの投稿について削除請求が来ています。7日以内に削除に反対する旨の返信がなければ、削除に同意したものとみなします」という趣旨の連絡(意見照会)をします。この期間内に投稿者から反論がなければ、プロバイダは投稿を削除しても免責されます。
送信防止措置請求は、プロバイダにこの免責要件を満たすためのアクションを促し、削除という判断をしやすくさせる効果を狙うものなのです。
3. 送信防止措置請求の具体的な手続きの流れ
弁護士に依頼した場合、一般的に以下の流れで進めます。
Step 1:請求先の特定
まず、問題の投稿が掲載されているサイトの運営者を正確に特定します。ウェブサイトの「会社概要」「運営者情報」などを確認し、法人の正式名称、代表者名、本店所在地などを調査します。
Step 2:送信防止措置請求書の作成
プロバイダ責任制限法の要件を満たした、法的に有効な請求書を作成します。書面には、主に以下の内容を盛り込みます。
- 請求者(被害者)の情報:氏名、住所、連絡先
- 代理人弁護士の情報
- 問題の投稿に関する情報:サイト名、URL、投稿日時、投稿内容など
- 侵害された権利:名誉権、プライバシー権、肖像権など
- 権利侵害の理由:なぜその投稿が、上記の権利を侵害していると言えるのかを、法律の条文や過去の裁判例などを引用しながら、具体的に、かつ論理的に主張します。
Step 3:請求書の送付
作成した請求書を、請求先のプロバイダに送付します。後日の裁判などで証拠となるよう、配達証明付きの内容証明郵便で送付するのが一般的です。
4. 送信防止措置請求の「限界」
この請求は強力な手段ですが、万能ではありません。以下のような限界があることを理解しておく必要があります。
- 強制力はない
あくまでプロバイダの任意の対応を促すものであり、削除を法的に強制する力はありません。 - 投稿者の反論に弱い
プロバイダが投稿者に意見照会を行った結果、投稿者が「権利侵害には当たらない」と反論してきた場合、プロバイダは板挟みを避けるため、削除に応じない判断をするケースがあります。 - 最終解決にならない場合も
上記の結果、結局は「被害者」と「投稿者」の間の争いとなり、問題を根本的に解決するためには、裁判所の手続きを利用せざるを得ない状況に至ることが少なくありません。
弁護士に相談するメリット
送信防止措置請求は、ご自身で行うことも不可能ではありませんが、その成功率を高め、次のステップにスムーズに進むためには、弁護士のサポートが重要です。
- 「権利侵害の明白性」を的確に主張できる
弁護士は、法律や裁判例の知識に基づき、「なぜこの投稿が違法なのか」を説得的に主張する書面を作成できます。これにより、プロバイダが意見照会を経ずに、任意削除に応じる可能性が高まります。 - プロバイダとの対等な交渉
相手は巨大企業であるプロバイダの法務部や顧問弁護士です。専門家である弁護士が代理人となることで、対等な立場で交渉を進め、軽くあしらわれるのを防ぎます。 - 裁判手続きへのスムーズな移行
送信防止措置請求で削除が実現しなかった場合でも、そこで終わりではありません。弁護士に依頼していれば、間髪をいれずに、削除を強制するための裁判手続き(削除仮処分申立て)に移行することができます。
まとめ
ご自身での削除依頼が通じなかったとしても、諦めるのはまだ早いです。「送信防止措置請求」は、法律を用いて、サイト運営者に削除を働きかける、次なる一手です。
しかし、この請求は、投稿者が反論すれば削除に至らないケースも多く、その先の裁判手続きまで見据えて戦略的に行う必要があります。請求書の書き方一つで、プロバイダの対応は大きく変わります。
「送信防止措置請求を試したいが、自分で書面を作る自信がない」「より確実に削除を実現したい」そうお考えの方は、この手続きを熟知した専門家である弁護士にご相談ください。
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、プロバイダの特性や最新の裁判例を踏まえた、実効性の高い送信防止措置請求をサポートしています。初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
長瀬総合の情報管理専門サイト
情報に関するトラブルは、方針決定や手続の選択に複雑かつ高度な専門性が要求されるだけでなく、迅速性が求められます。誹謗中傷対応に傾注する弁護士が、個人・事業者の皆様をサポートし、適切な問題の解決、心理的負担の軽減、事業の発展を支えます。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス
当事務所は多数の誹謗中傷の案件を担当しており、 豊富なノウハウと経験をもとに、企業の皆様に対して、継続的な誹謗中傷対策を提供しており、数多くの企業の顧問をしております。
企業の実情に応じて適宜顧問プランを調整することも可能ですので、お気軽にご連絡ください。